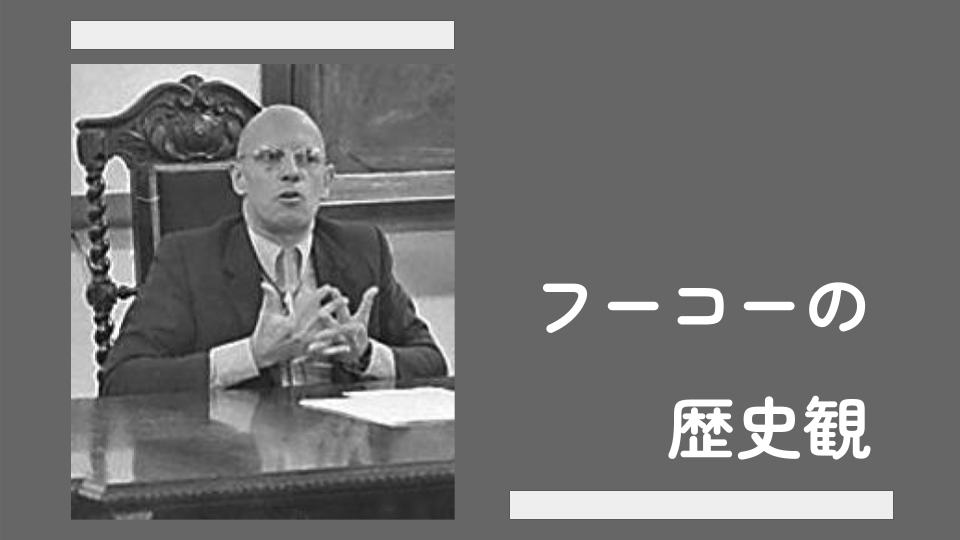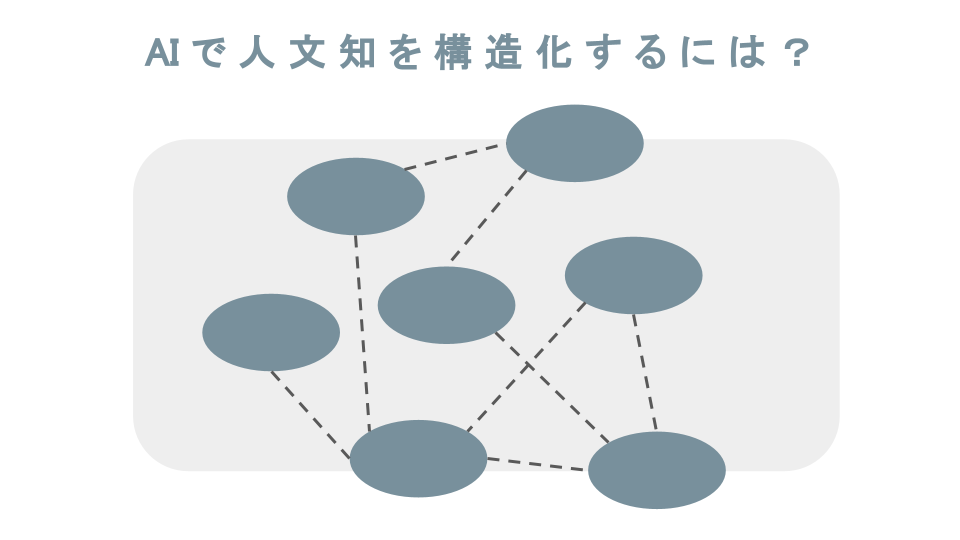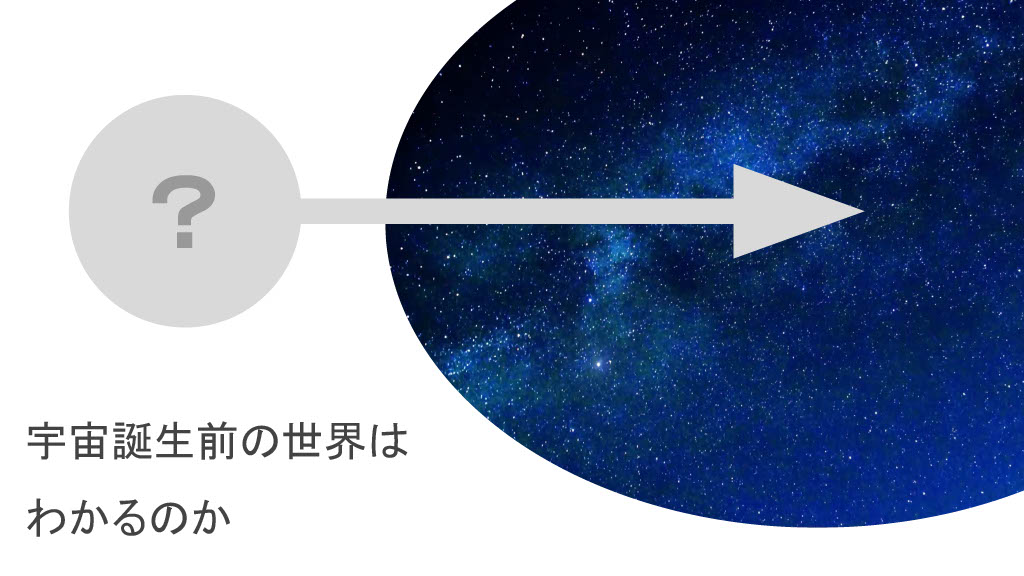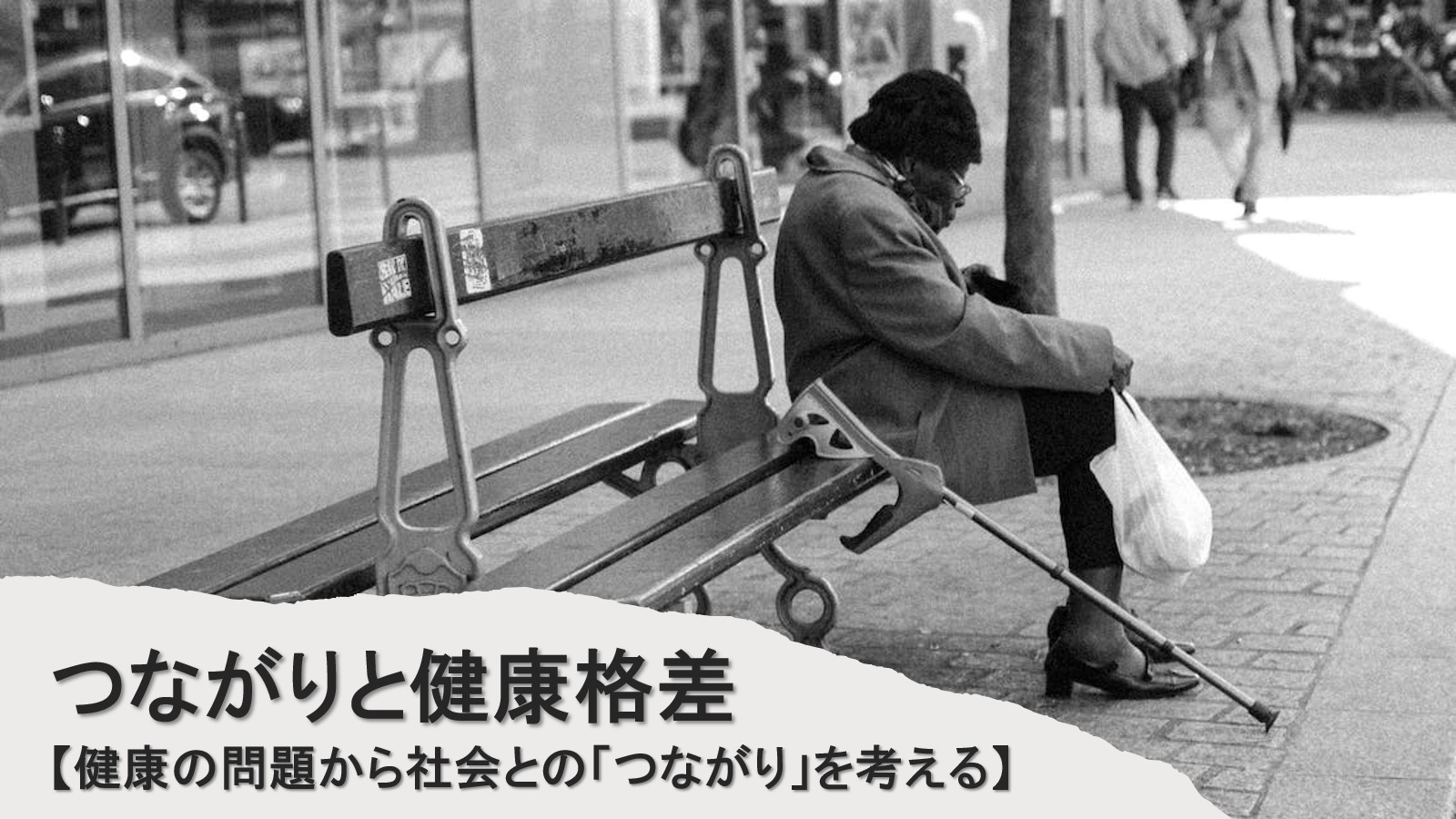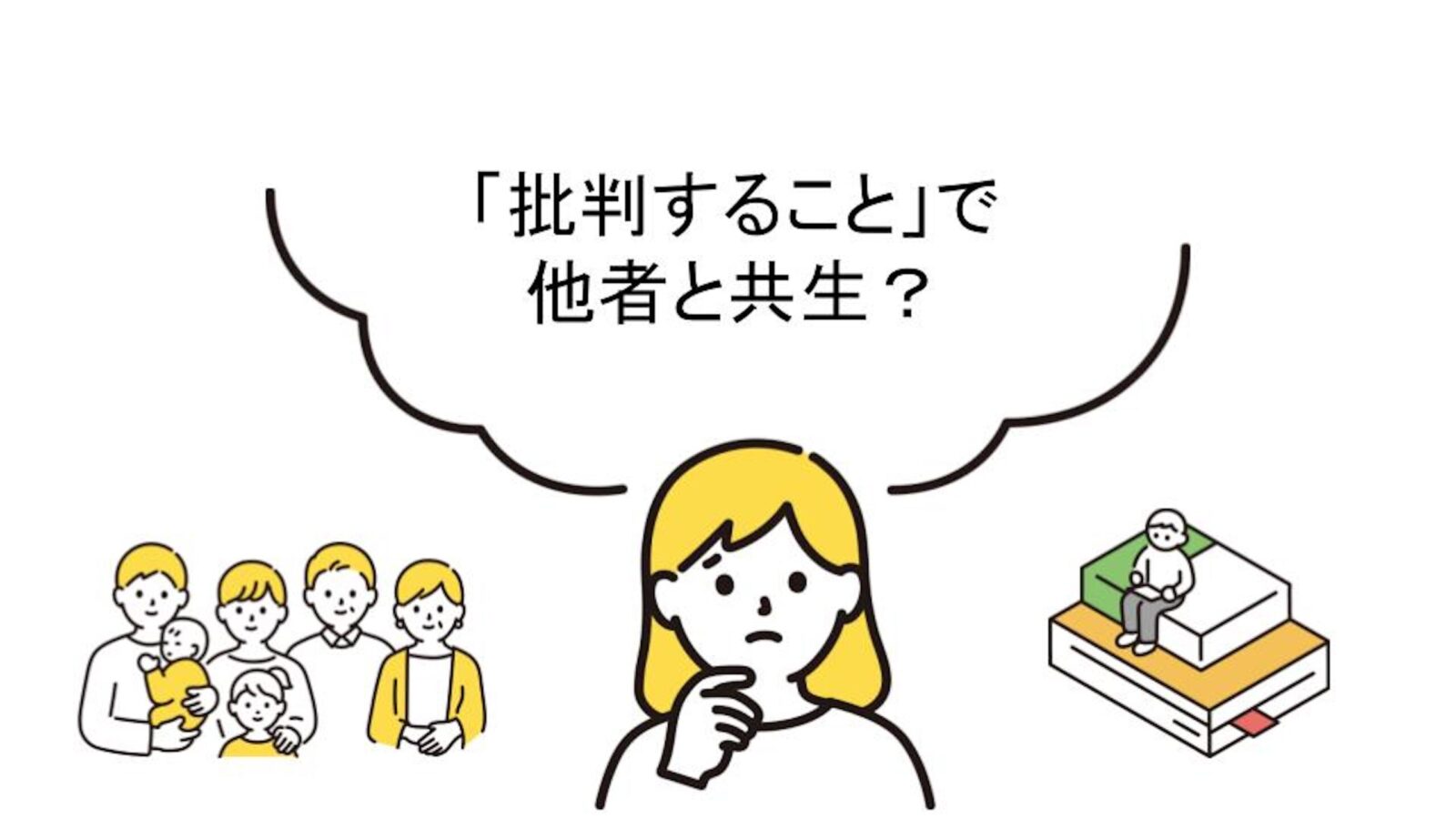2023/02/08
東アジア藝文書院(East Asian Academy for New Liberal Arts, 以下EAA)は、「東アジアからのリベラルアーツ」を標榜しつつ、北京大学をはじめとする国際的な研究ネットワークの下に、「世界」と「人間」を両面から問い直す新しい学問の創出を目指す、東京大学の研究教育センターです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
EAAは2019年度以来、「30年後の世界へ」を共通テーマとするオムニバス講義(学術フロンティア講義)を行なってきました。
2022年度の講義では、「30年後の世界へ―『共生』を問う」と題して、「共生」という概念について問い直すことが目指されました。
2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行により、他者と「共生」するということについて考えさせられることが増えました。
同居する家族が濃厚接触者になってしまうということ、感染症対策やワクチン接種についての考え方の違い、また、ロックダウンなどの対応は、「他者との共生」が脅威になりうるという事実を我々に突きつけてきました。
私たちはいかに他者と「共生」することができるのでしょうか。
「共生」を既定の事実として理想化するのではなく、私たちが生きるべきよりよい生のあり方について根本から捉え直す講義です。
その観点に立ち、哲学、文学、社会学、生物学など様々な分野の教員が講義をおこなっています。さらに、東京大学内だけでなく、北京大学、香港城市大学など、学外の講師による講義も行われました。
新型コロナウイルス感染症や生物の多様性、緊迫した国際情勢など、今を生きる私たちが直面している身近な問題も講義内で取り扱っているので、興味を持って視聴することができるでしょう。日常生活の中でなんとなく感じている息苦しさを和らげてくれるかもしれません。ぜひ、ラジオ感覚でリラックスしながら受講してみてください。
魯迅を再読する
今回ご紹介するのは、全13回の講義のうち第12回目の講義です。
講義をされるのは、東京大学総合文化研究科所属で比較文学を専門にされている王欽先生です。
この講義では、他者といかに共生するかという問いを、魯迅のテクストを手がかりに考えます。
「ノイズのような他者」といかに共生するか
想像してみてください。
ある真夏の昼下がり、カフェでカントの純粋理性批判を読んでいると、隣の席でカップルがイチャイチャし始めます。
文章が全然頭に入ってこないあなたは、文句を言いたいけれど、逆上されたり言い合いになったりしたら嫌なので我慢しています。内心ではひどく悪態をつきながら…。
これは、この授業の問いとなる「ノイズのような他者といかに共生するか」という場面の一例です。皆さんも似たような経験があるのではないでしょうか?
『阿金』との出会い
王欽先生が取り上げるのは、魯迅が晩年に書いた『阿金』というショートエッセイです。
タイトルの「阿金」とは、魯迅の家の斜め向かいの家に使える女中の名前です。「阿金」は、エッセイの中で魯迅の日常を乱す「ノイズのような他者」として描かれています。
原稿を執筆している時、阿金の友達が「阿金!」と彼女を呼ぶその声が、語り手の思考を妨げるのです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
雑音とは何か
ここまで「ノイズのような他者」と述べてきましたが、そもそも「ノイズ/雑音」とは何でしょうか?
王欽先生は、フランスの思想家・経済学者であるジャック・アタリの考察を取り上げ、雑音は音声や社会の秩序にとって常に侵略的であり暴力的であると言います。
最初のカフェのカップルを例にとると、彼らは確かにカフェの空間の秩序や読書を撹乱する存在でした。
どれだけきちんとした秩序を構成しようとしても否応なく入り込んでしまうノイズですが、見方を変えてみると、秩序を壊すことで新たな社会の可能性を我々に示唆してくれる存在でもあるのです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
阿金という力
語り手は、阿金の友達が彼女を呼ぶ騒がしい声を聞いて、原稿に「金」という文字を無意識に書いてしまったというエピソードを書いています。
彼女の影響力の大きさは語り手にとって衝撃的でした。
なぜなら、語り手が想定していた「女」は、男権社会において大して力を持たない存在だったからです。
ノイズとしての阿金の存在は、彼の30年来の信念と主張に動揺をもたらしたのです。
阿金の偉力=文学の力
語り手自身の秩序は、阿金というごく小さな存在によって撹乱されました。
また、歴史を振り返ってみると、中国社会は女性によって革新されてきました。
王欽先生は、阿金という偉力を通して歴史上の女性たちを理解し直していく、という読み方を提案します。
そこでは、女性たちが既存の社会秩序を動揺させ、新しい社会性を提示する力を持っているように、文学も政治に対して文学なりの偉力を持っているかもしれないと言います。
女性の力を捉え直す偉力を持つ「阿金」を、文学の可能性を示す作品として読むのです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
魯迅の意思
文学の役割について、魯迅の答えは「文学的に描くこと」だと言います。「阿金」というエッセイは、文学的な営みでできることとできないことを同時に提示してくれているのです。
1934年に書かれた「阿金」ですが、この時代は、日本の侵略に対して武器に相応しい文学作品を作るように要請されるという、魯迅にとってとても厳しい時期でした。
魯迅は武器としての文学を「それは文学ではない。」と考え、一種の抵抗として「阿金」を書きました。魯迅は、政治と文学の関係から後退し、真面目なことを避けようとしました。阿金というありふれた一人の女性を元にしてどんな文学作品ができるかを試行錯誤したのです。
文学の役割
魯迅は、文学的領域から政治哲学への翻訳という可能性を持たせながらも、あくまでも文学における話であるということにこだわりました。
普遍的であるかのような言葉は、実は分野を超えて翻訳できないということを伝えたかったのだと言います。
他者と共生するということ
共生や共存という言葉は素晴らしいもののようですが、実際は大変なことです。
王欽先生は、「素晴らしい共生」という側面を強調するのではなく、今日ではむしろ共生のどうにもならない側面に着目すべきだと言います。
魯迅は文学という限定のなかで、「ノイズとはこのようなものである」、「女性とはこのようなものである」ということを描きました。
日常生活の中で私たちはどうしていくべきかという問いに対する魯迅の答えは、
「どうにもならない。」ということだと言います。
我々にできることは、無意識のうちに他者に影響されて、他人の言葉を咀嚼し自分の言葉に変えていくことなのです。
ペンや飲み物、人、といった全てのものは「他者」です。
それらの異質な存在にぶつからない限り、自分と他者との共存は成り立ちません。
私たちは、他者という存在とぶつかって初めて自分の存在を意識するようになるのです。
授業動画を見て、阿金と文学から共生について考えてみませんか?
今回紹介した講義 : 30年後の世界へ ― 「共生」を問う(学術フロンティア講義)第12回 共生を求めること・共生を堪えること ― 魯迅を再読する 王 欽先生
<文/東京大学オンライン教育支援サポーター>
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
EAAは2019年度以来、「30年後の世界へ」を共通テーマとするオムニバス講義(学術フロンティア講義)を行なってきました。
2022年度の講義では、「30年後の世界へ―『共生』を問う」と題して、「共生」という概念について問い直すことが目指されました。
2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行により、他者と「共生」するということについて考えさせられることが増えました。
同居する家族が濃厚接触者になってしまうということ、感染症対策やワクチン接種についての考え方の違い、また、ロックダウンなどの対応は、「他者との共生」が脅威になりうるという事実を我々に突きつけてきました。
私たちはいかに他者と「共生」することができるのでしょうか。
「共生」を既定の事実として理想化するのではなく、私たちが生きるべきよりよい生のあり方について根本から捉え直す講義です。
その観点に立ち、哲学、文学、社会学、生物学など様々な分野の教員が講義をおこなっています。さらに、東京大学内だけでなく、北京大学、香港城市大学など、学外の講師による講義も行われました。
新型コロナウイルス感染症や生物の多様性、緊迫した国際情勢など、今を生きる私たちが直面している身近な問題も講義内で取り扱っているので、興味を持って視聴することができるでしょう。日常生活の中でなんとなく感じている息苦しさを和らげてくれるかもしれません。ぜひ、ラジオ感覚でリラックスしながら受講してみてください。
魯迅を再読する
今回ご紹介するのは、全13回の講義のうち第12回目の講義です。
講義をされるのは、東京大学総合文化研究科所属で比較文学を専門にされている王欽先生です。
この講義では、他者といかに共生するかという問いを、魯迅のテクストを手がかりに考えます。
「ノイズのような他者」といかに共生するか
想像してみてください。
ある真夏の昼下がり、カフェでカントの純粋理性批判を読んでいると、隣の席でカップルがイチャイチャし始めます。
文章が全然頭に入ってこないあなたは、文句を言いたいけれど、逆上されたり言い合いになったりしたら嫌なので我慢しています。内心ではひどく悪態をつきながら…。
これは、この授業の問いとなる「ノイズのような他者といかに共生するか」という場面の一例です。皆さんも似たような経験があるのではないでしょうか?
『阿金』との出会い
王欽先生が取り上げるのは、魯迅が晩年に書いた『阿金』というショートエッセイです。
タイトルの「阿金」とは、魯迅の家の斜め向かいの家に使える女中の名前です。「阿金」は、エッセイの中で魯迅の日常を乱す「ノイズのような他者」として描かれています。
原稿を執筆している時、阿金の友達が「阿金!」と彼女を呼ぶその声が、語り手の思考を妨げるのです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
雑音とは何か
ここまで「ノイズのような他者」と述べてきましたが、そもそも「ノイズ/雑音」とは何でしょうか?
王欽先生は、フランスの思想家・経済学者であるジャック・アタリの考察を取り上げ、雑音は音声や社会の秩序にとって常に侵略的であり暴力的であると言います。
最初のカフェのカップルを例にとると、彼らは確かにカフェの空間の秩序や読書を撹乱する存在でした。
どれだけきちんとした秩序を構成しようとしても否応なく入り込んでしまうノイズですが、見方を変えてみると、秩序を壊すことで新たな社会の可能性を我々に示唆してくれる存在でもあるのです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
阿金という力
語り手は、阿金の友達が彼女を呼ぶ騒がしい声を聞いて、原稿に「金」という文字を無意識に書いてしまったというエピソードを書いています。
彼女の影響力の大きさは語り手にとって衝撃的でした。
なぜなら、語り手が想定していた「女」は、男権社会において大して力を持たない存在だったからです。
ノイズとしての阿金の存在は、彼の30年来の信念と主張に動揺をもたらしたのです。
阿金の偉力=文学の力
語り手自身の秩序は、阿金というごく小さな存在によって撹乱されました。
また、歴史を振り返ってみると、中国社会は女性によって革新されてきました。
王欽先生は、阿金という偉力を通して歴史上の女性たちを理解し直していく、という読み方を提案します。
そこでは、女性たちが既存の社会秩序を動揺させ、新しい社会性を提示する力を持っているように、文学も政治に対して文学なりの偉力を持っているかもしれないと言います。
女性の力を捉え直す偉力を持つ「阿金」を、文学の可能性を示す作品として読むのです。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2022 王欽
魯迅の意思
文学の役割について、魯迅の答えは「文学的に描くこと」だと言います。「阿金」というエッセイは、文学的な営みでできることとできないことを同時に提示してくれているのです。
1934年に書かれた「阿金」ですが、この時代は、日本の侵略に対して武器に相応しい文学作品を作るように要請されるという、魯迅にとってとても厳しい時期でした。
魯迅は武器としての文学を「それは文学ではない。」と考え、一種の抵抗として「阿金」を書きました。魯迅は、政治と文学の関係から後退し、真面目なことを避けようとしました。阿金というありふれた一人の女性を元にしてどんな文学作品ができるかを試行錯誤したのです。
文学の役割
魯迅は、文学的領域から政治哲学への翻訳という可能性を持たせながらも、あくまでも文学における話であるということにこだわりました。
普遍的であるかのような言葉は、実は分野を超えて翻訳できないということを伝えたかったのだと言います。
他者と共生するということ
共生や共存という言葉は素晴らしいもののようですが、実際は大変なことです。
王欽先生は、「素晴らしい共生」という側面を強調するのではなく、今日ではむしろ共生のどうにもならない側面に着目すべきだと言います。
魯迅は文学という限定のなかで、「ノイズとはこのようなものである」、「女性とはこのようなものである」ということを描きました。
日常生活の中で私たちはどうしていくべきかという問いに対する魯迅の答えは、
「どうにもならない。」ということだと言います。
我々にできることは、無意識のうちに他者に影響されて、他人の言葉を咀嚼し自分の言葉に変えていくことなのです。
ペンや飲み物、人、といった全てのものは「他者」です。
それらの異質な存在にぶつからない限り、自分と他者との共存は成り立ちません。
私たちは、他者という存在とぶつかって初めて自分の存在を意識するようになるのです。
授業動画を見て、阿金と文学から共生について考えてみませんか?
今回紹介した講義 : 30年後の世界へ ― 「共生」を問う(学術フロンティア講義)第12回 共生を求めること・共生を堪えること ― 魯迅を再読する 王 欽先生
<文/東京大学オンライン教育支援サポーター>