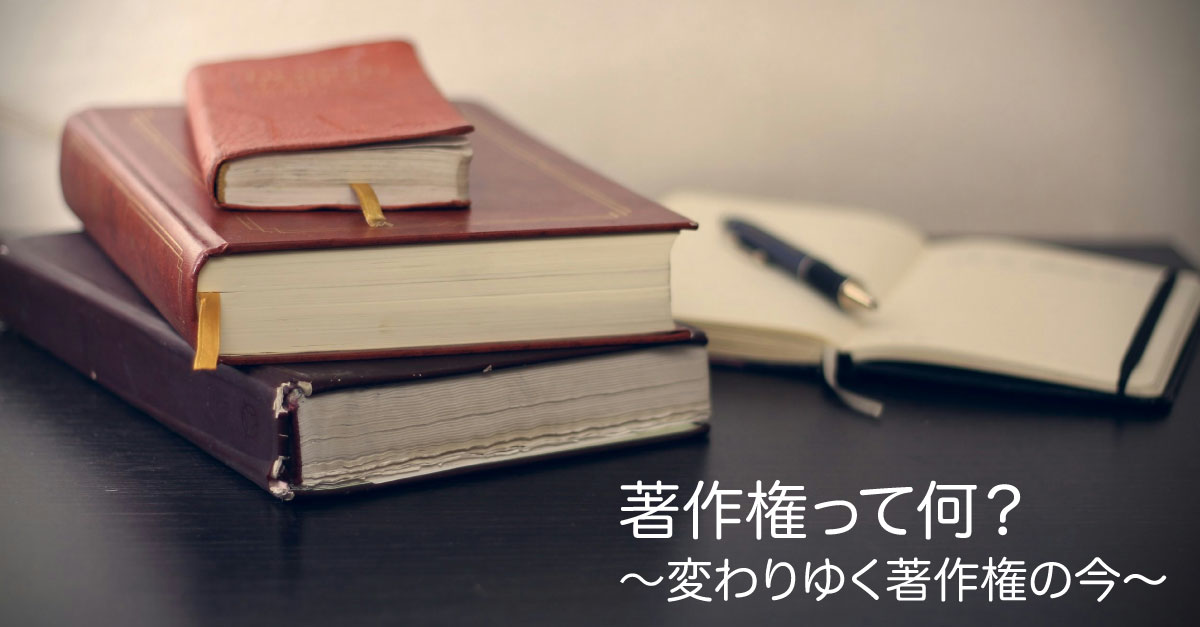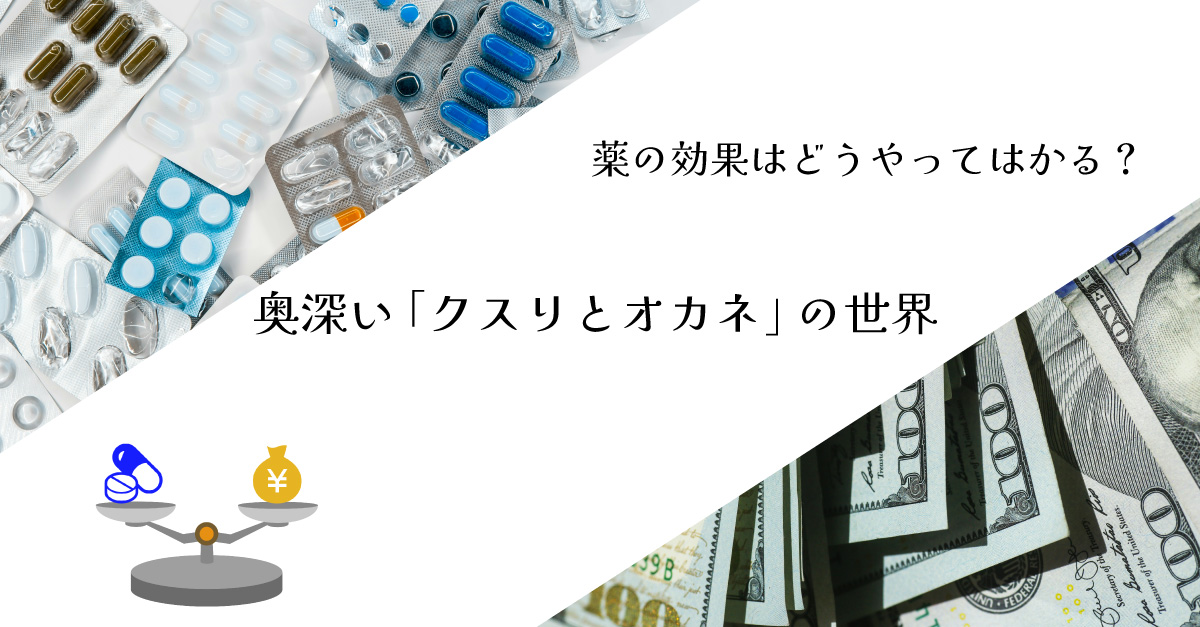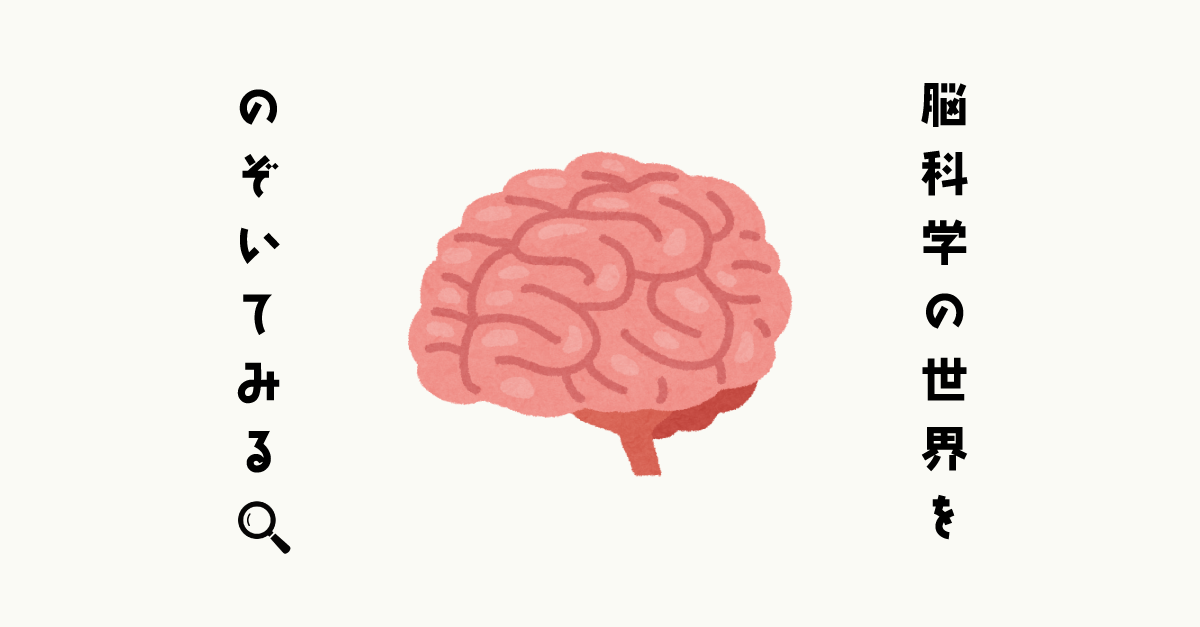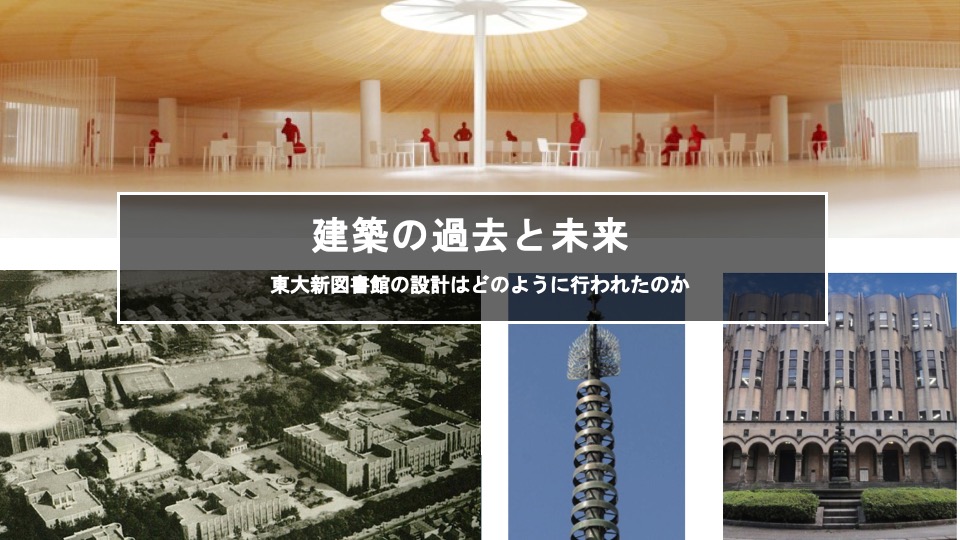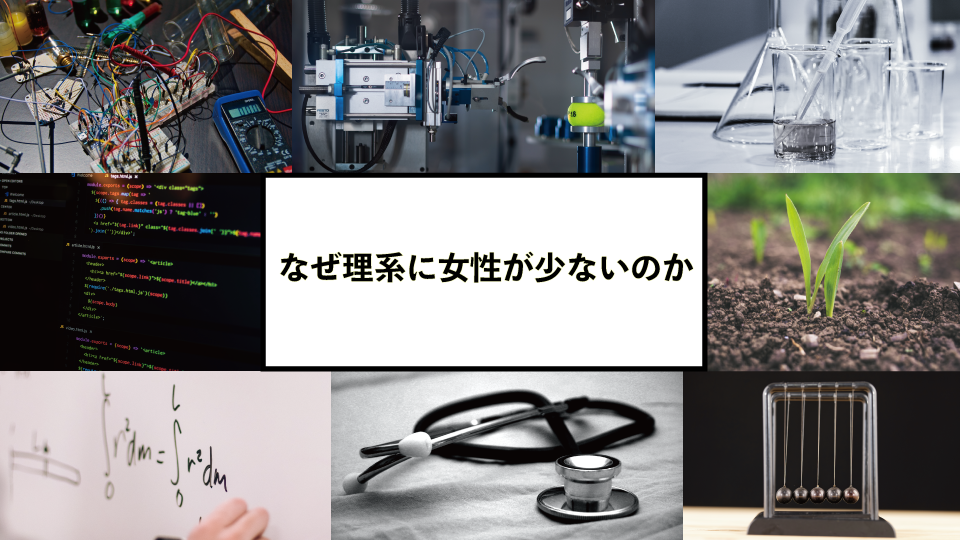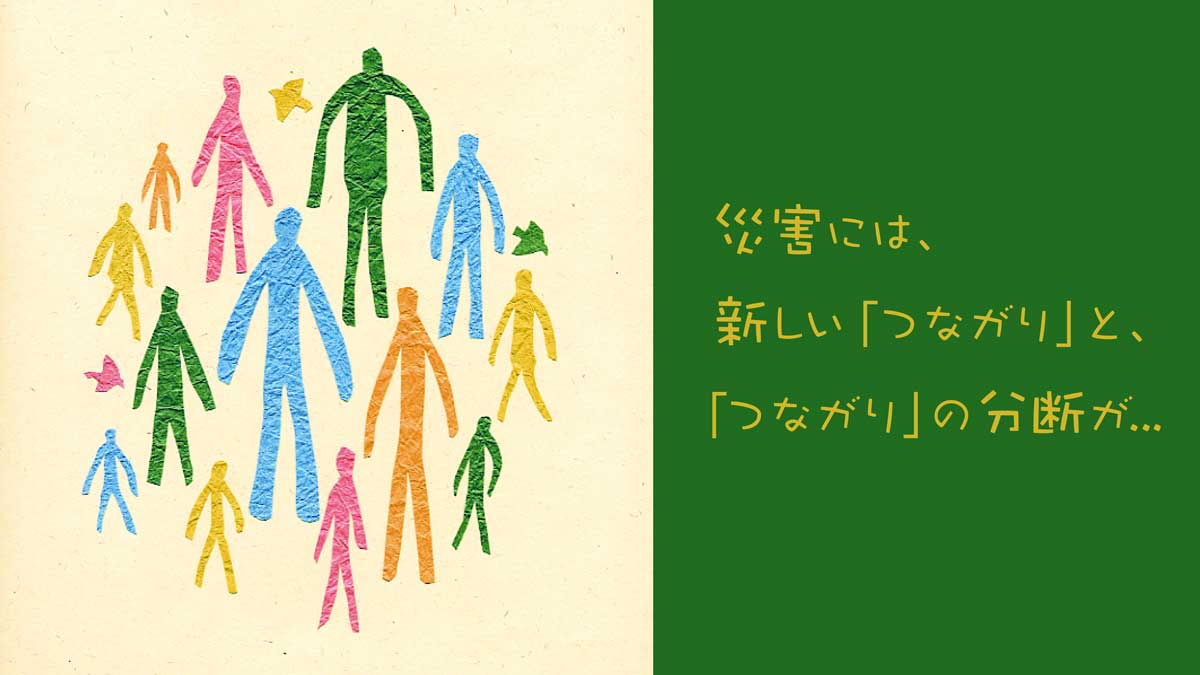
2024/07/31
本日ご紹介するのは、「人と物」「人と動物」「人と人」など、様々な「つながり」を見つめ直すコース、
「つながり」から読み解く人と世界(朝日講座「知の調和―世界をみつめる 未来を創る」2019年度講義)
から、第10回『災害とつながり―社会関係の中で生きる人間像―』です。
講師は、災害情報論と社会心理学がご専門の、田中 淳(たなか あつし)先生です。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
社会学から見る災害研究
この授業は、東日本大震災から8年という年に行われました。講義には、東日本大震災だけでなく、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、四川大地震、令和元年(2019年)の台風19号など、様々な災害が例として挙げられます。
「災害研究」という言葉を聞くと、地震研究のような理学的な学問、また、防災には工学的な学問のイメージを抱かれるのではないでしょうか。長らく防災に取り組んできた田中先生は、「人の命を救う防災には、全ての学問が関係している」と語ります。災害に立ち向かうには、財政の健全化が必要であり、必要に応じて法律改正があり、また医療や国際関係にも関係があります。「生きること」などを考える際には、宗教学も関係してくるでしょう。そして、東大は、世界的に見ても早い段階で、社会学が災害研究に参入していました。
「つながり」について考えてみよう
「つながり」という言葉は、何か明るくて良い意味合いを持っていそうです。東日本大震災の際にも、さかんに「絆」という言葉が謳われました。しかし、災害においては、この「つながり」の全てがポジティブに捉えられるわけではありません。
災害は、新しい「つながり」を生み出すこともあれば、同時に、「つながり」を分断することもあると、先生は言います。一体、どういうことでしょうか。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
いくつか、講義の中で印象に残ったエピソードを取り上げて、ご紹介します。
災害で損なわれる「つながり」
災害で失うものには、どのようなものがあるでしょうか。
まず、人の命や健康が損なわれます。そして、家や家財、財産、社会システムなど、生活基盤が失われます。また、生き残った人の間でも、コミュニケーションのすれ違いを起こしたり、元々あったコミュニティが瓦解したりと、まさに「つながり」が壊れてしまうことがあります。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
「つながり」に影響されて意外に個人で決断できないことが多い
皆さんは、日頃、自動販売機でジュースを買うときに、どの程度、未来や影響を考えて、購入する1本を選び抜いていますか?「自分がこのメーカーさんのジュースを選んだことによって、違うメーカーさんが潰れてしまうかもしれない」などと考えたことはありますか?おそらく、誰もそんなに深く考えておらず、気楽に数秒で決断して購入していることでしょう。
被災すると、ありとあらゆる決断を瞬時に迫られる場面が出てきます。様々な選択肢や起こりうる問題などを検討しつつ、慎重に選び抜かなければならない重要な事項なのに、多くの場合は、短いスパンでどんどん決めていかなければなりません。
津波の警報が出た後に、すぐに避難するか、しないか。避難所に行くか、車中泊するか。元の町に戻るか、移転するか。
こういったことは、意外に、自分1人で決められるものではありません。様々な個人の計画には、家族・地域・共同体・行政などの意向が、強く影響してきます。
例えば、自分が元の家に戻りたいと思っていても、家族は、同じ土地で再び同じ目に遭うことを恐れて反対するかもしれません。また、自分の一家ではその地域に帰りたいと考えていても、元々住んでいた住民がどの程度戻るのかによって将来の地域の活性や復興の度合いが変わってしまいますから、多くの他者の振る舞いが自分の生活に影響を与えることになります。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
また、印象的だったのは、「避難行動は、実は一般に言われるほど個人で決めるものではない」というお話です。地震や津波の警報が出た際、本当は避難しようと思わなかった人も、周りに合わせて避難しているケースがあります。これは、避難するかどうかということは、個人の意志によって決定している他に、かなり大きく「規範」が影響するということです。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
顕在化されたり分断されたりする「つながり」
普段、1人の人間は、社会の中でいくつもの役割を持って暮らしています。例えば、田中先生の場合は、ご自身で、こんな顔を持っていると考えているそうですよ。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
このように多様な側面を持つ人が、もしも災害に遭うと、たちまち「被災者」というカテゴリに入れられてしまうことがあります。
このことは、どのような影響をもたらすでしょうか。
例えば、被災すると、避難所や仮設住宅で、常にボランティアさんに助けてもらったり、常に炊き出しで食事を貰ったりする側になります。つまり、ずっと「被災者」という役割になってしまうのです。普段、お店でお金を出して商品やサービスを買う際には、作ってくれた人や販売してくれた人に引け目を感じることはありませんが、無償で何かを受け取るだけの側になると、申し訳ない気持ちが湧いてきて、その状況が続くと、だんだん辛くなってきます。これを「互酬性の顕在化」と呼びます。このような気持ちを抱え続けなければならないのは、健全な環境とは言えません。
また、被災者は、報道などによって多くの人の目に晒されます。その際、「被災者」は、しばしば、1つの定まった意見を持った人物であるかのように伝えられてしまうことがあります。
例えば、東日本大震災の際、校庭で待つように指示された多くの小学生が津波から逃げ遅れてしまった「大川小学校」という学校があります。ご遺族は、当時の小学校の方針に対して「賛成なのか、反対なのか」など、意見を述べるよう迫られることがあります。迫られて、どちらか述べることによって、分断が生まれてしまうのだと言います。ご遺族の立場や気持ちは、白か黒かではなく揺れ動くものであり、一定ではありません。つまり、「怒りもある」「しかし、先生方のお子さんも逃げ遅れているのも知っている」といった具合です。
被災者は、他の形でも、分断の危機に晒されることがあります。
まず、一つ目は、「内外問題」です。
例えば、田中先生が他の地域で起きた災害の現場に出向いていくと、先生は「東京の人」と呼ばれます。また、同じ地域の中でも、被害の程度によって、「なんだ、⚪︎⚪︎市の人か、大したことないじゃないか、うちはもっと酷い目に遭ったんだ」「あなたには、こんな酷い被害に遭った私の気持ちは分からない」といったランク付けが生じます。生々しい話ですが、被害の大きさによって、下りる助成金や義援金の額も変わります。そこには、お互い、自分の気持ちを分かってほしいけど、そう簡単に分かってほしくもないという、複雑な心理があるのです。
次に、災害後、長い時間が経ってくると、次第に被災者は世間から厳しい目を向けられるようになると言います。例えば、公的な経済支援を受けていることについて、妬まれて嫌味を言われたりするようになることがあるそうです。何もかも失って、なかなか元の仕事や生活を取り戻すことが難しく、そのエネルギーも湧いてこないときに、このような視線や言葉を向けられるのは、どれほど辛いことでしょうか。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
今だからこそこの講義がよく理解できるかも?
さて、ここまで講義内容を紹介してまいりました。
2019年に行われたこの講義ですが、今だからこそ、より多くの人が理解できる内容なのではないかと感じました。
災害について話す際は、多くの場合、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、熊本地震、東日本大震災など、多くの人が知る大きな出来事を例に挙げて話します。実際に何らかの災害に遭ったことがある方は、ご自身が体験したことの記憶と重ねて、つぶさにイメージを思い浮かべながら話を聞くでしょう。そして、より多くの、幸いにも大規模な災害に遭ったことがない人は、頭の片隅からニュースで見聞きした様子を引っ張り出してきて、なんとか自分に引き寄せて想像しながら、話を聞くでしょう。実際に体験していないことを想像することには限界がありますから、世代や出身地域などのバックグラウンドによって、イメージを描いたり議論したりする際、個々の理解度には様々な差が生じていたことと思います。
しかし、2020年以降の我々はどうでしょうか。この記事を読んでいるほとんどの人が、世代や地域の枠を超えて、一様に、いわゆる「コロナ禍」を経験しています。現在の我々は、災害時に生まれる新たな「つながり」や、災害時に起きる分断を、ありありと思い浮かべることができるようになっているでしょう。
例えば、授業で語られた下記の2つのことは、我々がかなりよく知っていることです。
まず、「何か出来事が発生すると、普段隠れている(地下に潜められていた)偏見・差別・社会構造の弱さなどが露呈する」ということについて考えてみましょう。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
コロナ禍では、エッセンシャルワーカーの労働環境、外国人差別、行政への不満など、元々あった様々な問題が、さらに浮き彫りになりました。もっと小さな単位では、「ステイホーム」によって、普段はバラバラに過ごしていた家族が四六時中、顔を突き合わせていることにより、家族間の価値観の相違などに気付いたというご家庭もあるでしょう。
そして、次に、社会システムの変容についても、今ならば実感を持って理解することができるでしょう。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
災害が起きると、通常運行していた社会システムは、停滞したり、その機能をぐんと低下させてしまいます。そして、緊急の代替として、応急的なシステムが発動します。しかし、それはあくまでも臨時のものであって、効率が悪いため、また元に戻されてゆきます。(例えば、震災が起きた際には、臨時的に行政の職員が生活用品や飲食物を配布しますが、これらはコンビニエンスストアやスーパーマーケットの物流が復旧したら、そちらの方が圧倒的に効率が良いでしょう。)被災者は、この度重なる環境変化に見舞われ、そして、順応していかなければなりません。
このことは、コロナ禍では、多くの学校が通常の授業の代わりにオンライン授業を取り入れ、やがて1〜2年掛けて、元の「対面」授業に戻していったことに当てはめられるでしょう。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
この記事内ではご紹介しきれませんでしたが、この講義では、被災者が置かれる状況や心理状態について、とても丁寧に説明されています。ぜひ、講義動画をご覧ください。
「つながり」の分断がどのようなものか、よく知るようになった我々は、その経験を持って、前よりもうまく、新たな「つながり」を生み出す方法を考えられるようになっていると思いたいものです。
<文・加藤なほ>
今回紹介した講義:「つながり」から読み解く人と世界(朝日講座「知の調和―世界をみつめる 未来を創る」2019年度講義) 第10回 災害とつながり―社会関係の中で生きる人間像― 田中淳先生
●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。
「つながり」から読み解く人と世界(朝日講座「知の調和―世界をみつめる 未来を創る」2019年度講義)
から、第10回『災害とつながり―社会関係の中で生きる人間像―』です。
講師は、災害情報論と社会心理学がご専門の、田中 淳(たなか あつし)先生です。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
社会学から見る災害研究
この授業は、東日本大震災から8年という年に行われました。講義には、東日本大震災だけでなく、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、四川大地震、令和元年(2019年)の台風19号など、様々な災害が例として挙げられます。
「災害研究」という言葉を聞くと、地震研究のような理学的な学問、また、防災には工学的な学問のイメージを抱かれるのではないでしょうか。長らく防災に取り組んできた田中先生は、「人の命を救う防災には、全ての学問が関係している」と語ります。災害に立ち向かうには、財政の健全化が必要であり、必要に応じて法律改正があり、また医療や国際関係にも関係があります。「生きること」などを考える際には、宗教学も関係してくるでしょう。そして、東大は、世界的に見ても早い段階で、社会学が災害研究に参入していました。
「つながり」について考えてみよう
「つながり」という言葉は、何か明るくて良い意味合いを持っていそうです。東日本大震災の際にも、さかんに「絆」という言葉が謳われました。しかし、災害においては、この「つながり」の全てがポジティブに捉えられるわけではありません。
災害は、新しい「つながり」を生み出すこともあれば、同時に、「つながり」を分断することもあると、先生は言います。一体、どういうことでしょうか。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
いくつか、講義の中で印象に残ったエピソードを取り上げて、ご紹介します。
災害で損なわれる「つながり」
災害で失うものには、どのようなものがあるでしょうか。
まず、人の命や健康が損なわれます。そして、家や家財、財産、社会システムなど、生活基盤が失われます。また、生き残った人の間でも、コミュニケーションのすれ違いを起こしたり、元々あったコミュニティが瓦解したりと、まさに「つながり」が壊れてしまうことがあります。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
「つながり」に影響されて意外に個人で決断できないことが多い
皆さんは、日頃、自動販売機でジュースを買うときに、どの程度、未来や影響を考えて、購入する1本を選び抜いていますか?「自分がこのメーカーさんのジュースを選んだことによって、違うメーカーさんが潰れてしまうかもしれない」などと考えたことはありますか?おそらく、誰もそんなに深く考えておらず、気楽に数秒で決断して購入していることでしょう。
被災すると、ありとあらゆる決断を瞬時に迫られる場面が出てきます。様々な選択肢や起こりうる問題などを検討しつつ、慎重に選び抜かなければならない重要な事項なのに、多くの場合は、短いスパンでどんどん決めていかなければなりません。
津波の警報が出た後に、すぐに避難するか、しないか。避難所に行くか、車中泊するか。元の町に戻るか、移転するか。
こういったことは、意外に、自分1人で決められるものではありません。様々な個人の計画には、家族・地域・共同体・行政などの意向が、強く影響してきます。
例えば、自分が元の家に戻りたいと思っていても、家族は、同じ土地で再び同じ目に遭うことを恐れて反対するかもしれません。また、自分の一家ではその地域に帰りたいと考えていても、元々住んでいた住民がどの程度戻るのかによって将来の地域の活性や復興の度合いが変わってしまいますから、多くの他者の振る舞いが自分の生活に影響を与えることになります。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
また、印象的だったのは、「避難行動は、実は一般に言われるほど個人で決めるものではない」というお話です。地震や津波の警報が出た際、本当は避難しようと思わなかった人も、周りに合わせて避難しているケースがあります。これは、避難するかどうかということは、個人の意志によって決定している他に、かなり大きく「規範」が影響するということです。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
顕在化されたり分断されたりする「つながり」
普段、1人の人間は、社会の中でいくつもの役割を持って暮らしています。例えば、田中先生の場合は、ご自身で、こんな顔を持っていると考えているそうですよ。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
このように多様な側面を持つ人が、もしも災害に遭うと、たちまち「被災者」というカテゴリに入れられてしまうことがあります。
このことは、どのような影響をもたらすでしょうか。
例えば、被災すると、避難所や仮設住宅で、常にボランティアさんに助けてもらったり、常に炊き出しで食事を貰ったりする側になります。つまり、ずっと「被災者」という役割になってしまうのです。普段、お店でお金を出して商品やサービスを買う際には、作ってくれた人や販売してくれた人に引け目を感じることはありませんが、無償で何かを受け取るだけの側になると、申し訳ない気持ちが湧いてきて、その状況が続くと、だんだん辛くなってきます。これを「互酬性の顕在化」と呼びます。このような気持ちを抱え続けなければならないのは、健全な環境とは言えません。
また、被災者は、報道などによって多くの人の目に晒されます。その際、「被災者」は、しばしば、1つの定まった意見を持った人物であるかのように伝えられてしまうことがあります。
例えば、東日本大震災の際、校庭で待つように指示された多くの小学生が津波から逃げ遅れてしまった「大川小学校」という学校があります。ご遺族は、当時の小学校の方針に対して「賛成なのか、反対なのか」など、意見を述べるよう迫られることがあります。迫られて、どちらか述べることによって、分断が生まれてしまうのだと言います。ご遺族の立場や気持ちは、白か黒かではなく揺れ動くものであり、一定ではありません。つまり、「怒りもある」「しかし、先生方のお子さんも逃げ遅れているのも知っている」といった具合です。
被災者は、他の形でも、分断の危機に晒されることがあります。
まず、一つ目は、「内外問題」です。
例えば、田中先生が他の地域で起きた災害の現場に出向いていくと、先生は「東京の人」と呼ばれます。また、同じ地域の中でも、被害の程度によって、「なんだ、⚪︎⚪︎市の人か、大したことないじゃないか、うちはもっと酷い目に遭ったんだ」「あなたには、こんな酷い被害に遭った私の気持ちは分からない」といったランク付けが生じます。生々しい話ですが、被害の大きさによって、下りる助成金や義援金の額も変わります。そこには、お互い、自分の気持ちを分かってほしいけど、そう簡単に分かってほしくもないという、複雑な心理があるのです。
次に、災害後、長い時間が経ってくると、次第に被災者は世間から厳しい目を向けられるようになると言います。例えば、公的な経済支援を受けていることについて、妬まれて嫌味を言われたりするようになることがあるそうです。何もかも失って、なかなか元の仕事や生活を取り戻すことが難しく、そのエネルギーも湧いてこないときに、このような視線や言葉を向けられるのは、どれほど辛いことでしょうか。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
今だからこそこの講義がよく理解できるかも?
さて、ここまで講義内容を紹介してまいりました。
2019年に行われたこの講義ですが、今だからこそ、より多くの人が理解できる内容なのではないかと感じました。
災害について話す際は、多くの場合、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、熊本地震、東日本大震災など、多くの人が知る大きな出来事を例に挙げて話します。実際に何らかの災害に遭ったことがある方は、ご自身が体験したことの記憶と重ねて、つぶさにイメージを思い浮かべながら話を聞くでしょう。そして、より多くの、幸いにも大規模な災害に遭ったことがない人は、頭の片隅からニュースで見聞きした様子を引っ張り出してきて、なんとか自分に引き寄せて想像しながら、話を聞くでしょう。実際に体験していないことを想像することには限界がありますから、世代や出身地域などのバックグラウンドによって、イメージを描いたり議論したりする際、個々の理解度には様々な差が生じていたことと思います。
しかし、2020年以降の我々はどうでしょうか。この記事を読んでいるほとんどの人が、世代や地域の枠を超えて、一様に、いわゆる「コロナ禍」を経験しています。現在の我々は、災害時に生まれる新たな「つながり」や、災害時に起きる分断を、ありありと思い浮かべることができるようになっているでしょう。
例えば、授業で語られた下記の2つのことは、我々がかなりよく知っていることです。
まず、「何か出来事が発生すると、普段隠れている(地下に潜められていた)偏見・差別・社会構造の弱さなどが露呈する」ということについて考えてみましょう。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
コロナ禍では、エッセンシャルワーカーの労働環境、外国人差別、行政への不満など、元々あった様々な問題が、さらに浮き彫りになりました。もっと小さな単位では、「ステイホーム」によって、普段はバラバラに過ごしていた家族が四六時中、顔を突き合わせていることにより、家族間の価値観の相違などに気付いたというご家庭もあるでしょう。
そして、次に、社会システムの変容についても、今ならば実感を持って理解することができるでしょう。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
災害が起きると、通常運行していた社会システムは、停滞したり、その機能をぐんと低下させてしまいます。そして、緊急の代替として、応急的なシステムが発動します。しかし、それはあくまでも臨時のものであって、効率が悪いため、また元に戻されてゆきます。(例えば、震災が起きた際には、臨時的に行政の職員が生活用品や飲食物を配布しますが、これらはコンビニエンスストアやスーパーマーケットの物流が復旧したら、そちらの方が圧倒的に効率が良いでしょう。)被災者は、この度重なる環境変化に見舞われ、そして、順応していかなければなりません。
このことは、コロナ禍では、多くの学校が通常の授業の代わりにオンライン授業を取り入れ、やがて1〜2年掛けて、元の「対面」授業に戻していったことに当てはめられるでしょう。
UTokyo Online Education 東京大学朝日講座 2019 田中 淳
この記事内ではご紹介しきれませんでしたが、この講義では、被災者が置かれる状況や心理状態について、とても丁寧に説明されています。ぜひ、講義動画をご覧ください。
「つながり」の分断がどのようなものか、よく知るようになった我々は、その経験を持って、前よりもうまく、新たな「つながり」を生み出す方法を考えられるようになっていると思いたいものです。
<文・加藤なほ>
今回紹介した講義:「つながり」から読み解く人と世界(朝日講座「知の調和―世界をみつめる 未来を創る」2019年度講義) 第10回 災害とつながり―社会関係の中で生きる人間像― 田中淳先生
●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。