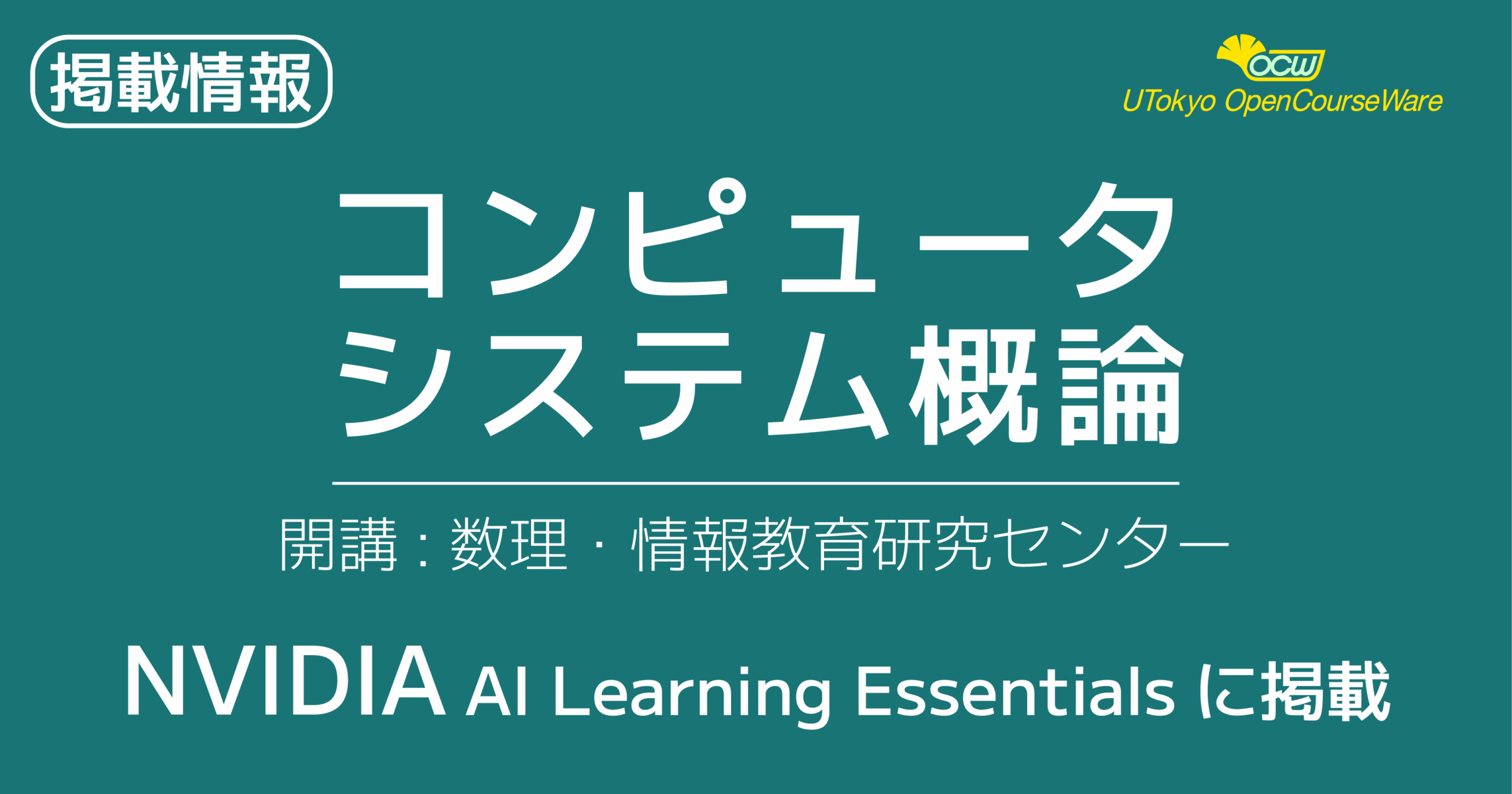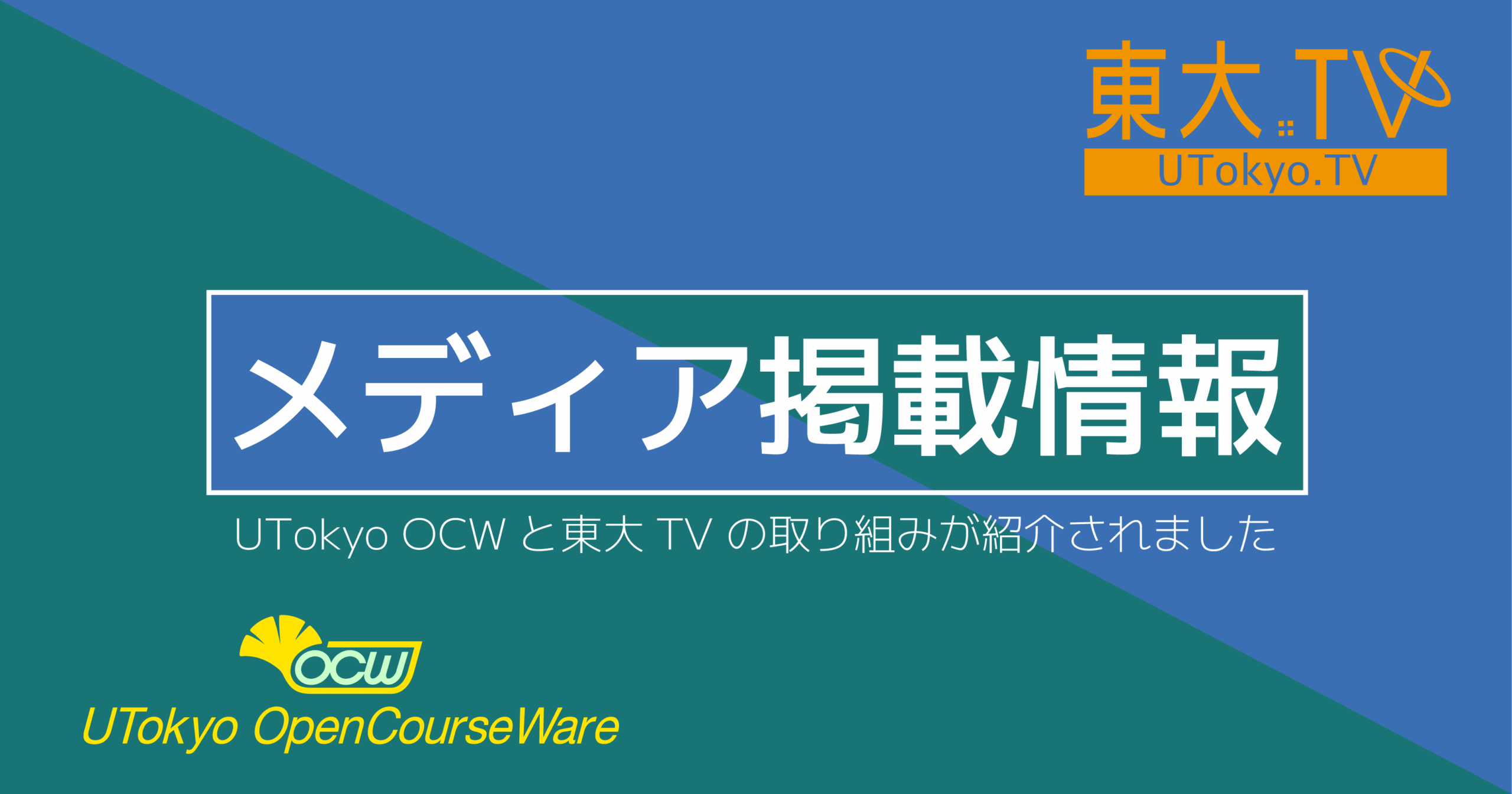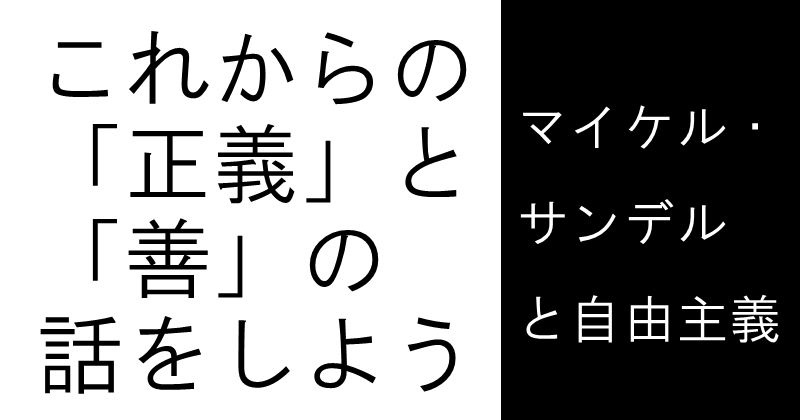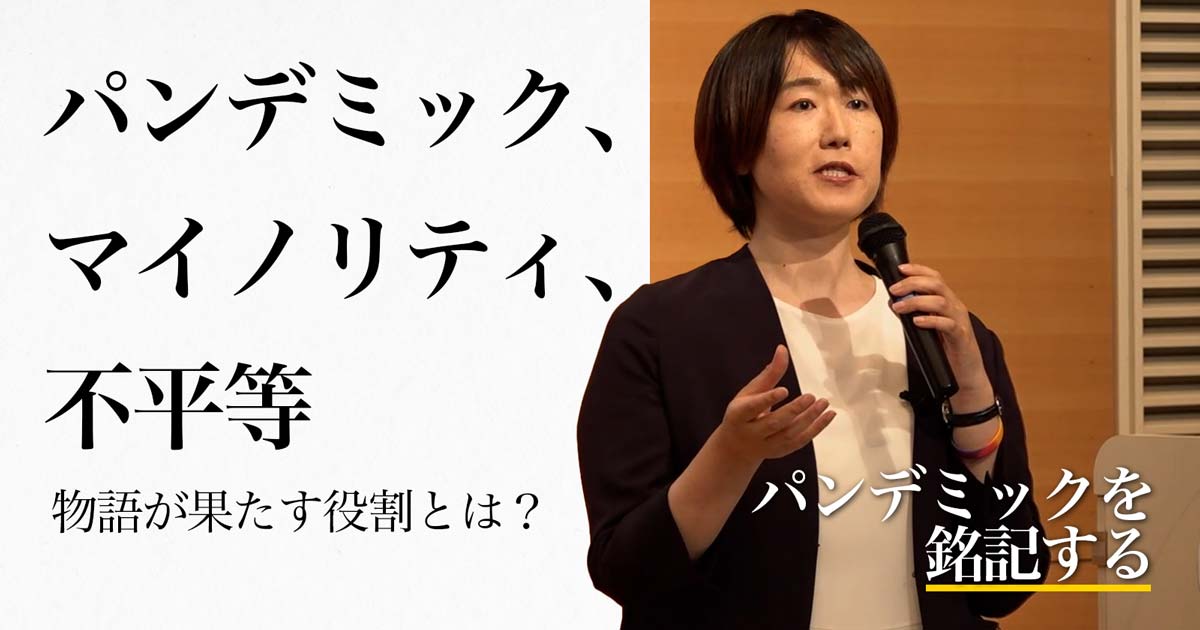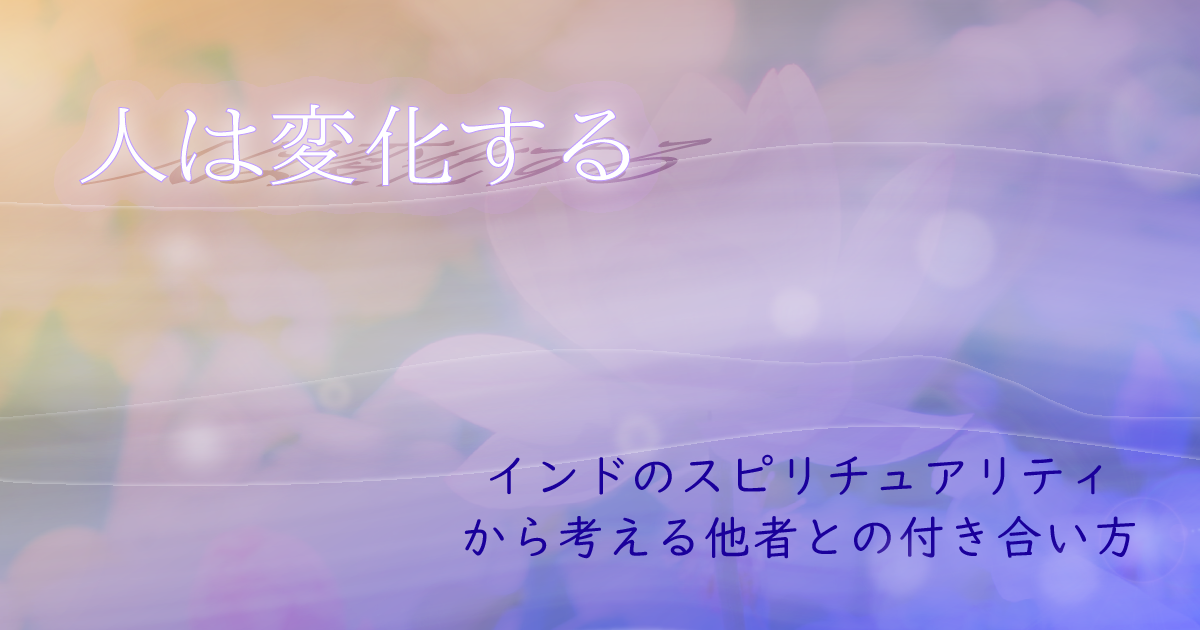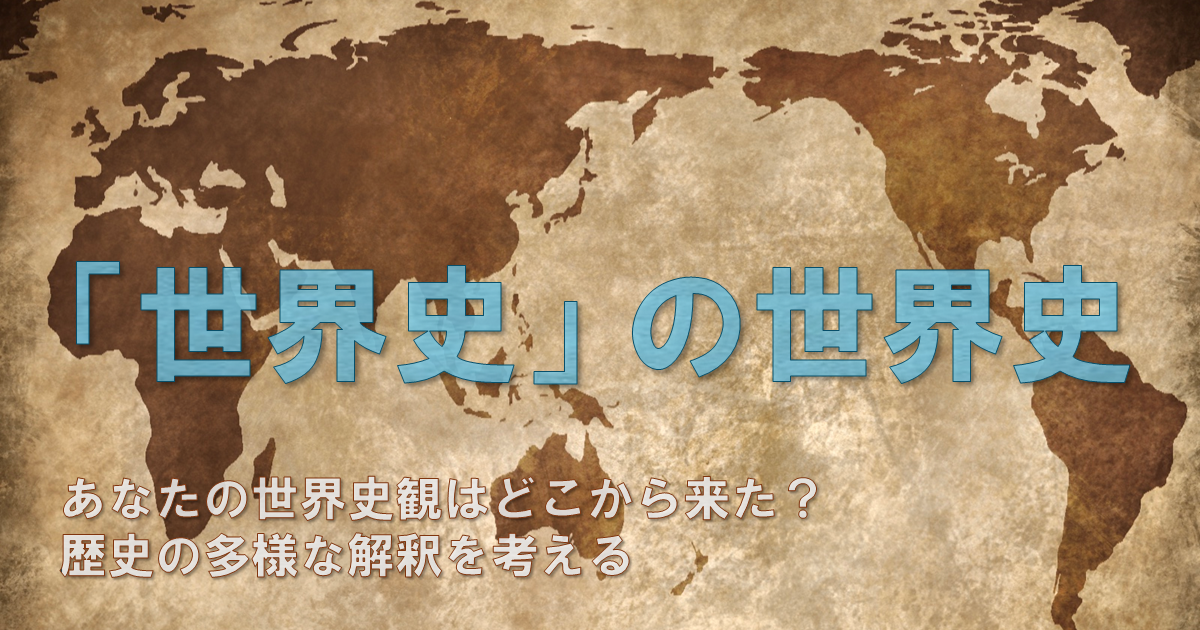2025/08/14
「楽しいとは何か?」
そう問われたとき、私たちは意外と答えに詰まります。自分が何をしているときに楽しいのか、どのような条件を満たすと「楽しい」と感じるのか、実は明確には分かっていないのかもしれません。
哲学の世界では、一般に「美しい」の方が「楽しい」よりも高尚なものとされてきました。そのため、「美しい」に関する議論は数多く存在しますが、「楽しい」についての哲学的議論は多くありません。楽しみそのもの、そして楽しむためだけに存在する「嗜好品」についても同様です。
この「嗜好品」という言葉はドイツ語の「Genußmittel」を翻訳したものです。「Genießen」は「楽しむ」「味わう」といった意味の動詞で、「Genuß」はその名詞形。「Mittel」は「手段」ですから、「Genußmittel」とは「楽しむための手段」、すなわち嗜好品というわけです。
講義では、「Genuß」を「享受の快」と訳し、この概念を通してカントが人間の楽しみをどう捉えていたのか、そしてその考えが現代社会においてどのような意味を持ちうるのかを考えていきます。
今回ご紹介するのは、2025年度開講の学術フロンティア講義(30年後の世界へーー変わる教養、変える教養)「第2回 享受の快--カントと嗜好品」。講師は『暇と退屈の倫理学』『手段からの解放』などの著書で知られる哲学者・國分功一郎先生です。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2025S 國分功一郎
カントの理論体系
早速、本題に入ります。まずは、カントの理論体系を踏まえ「享受の快」がどう位置付けられているか見ていきます。
カントには三つの主著、『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』があり、それぞれ人間の異なる能力を扱っています。この三冊をもって、カントは人間の経験全体を説明しようと試みました。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2025S 國分功一郎
『純粋理性批判』では認識能力を、『実践理性批判』では欲求能力、すなわち「善をイメージしてそれを実現したいと欲求して行為する」能力を吟味しています。そして、『判断力批判』が対象とするのは人間の「感情能力」です。(ここでの「批判」はケチをつけることではなく、吟味するという意味です。)
表が示しているように、カントはそれぞれの能力を高次と低次に区別しています。たとえば、欲求能力においては「やらなければならないからやる」ことが高次とされ、「何かのためにやる」ことは低次とされます。
人間の「快」は4種類しかない?
そして、カントによれば、人間にとっての「快」は4種類に分類されます。(「快」は、快楽や快感とも訳せますが意味が限定されてしまうのでここでは「快」と訳します。)
快の対象は、快適なもの、美しいもの、崇高なもの、(端的に)善いものの4つのいずれかに当てはまると考えられ、このうち「快適なもの」(Angenehmen)という概念が、「享受の快」に結び付けられています。
4つの快の対象の配置
では、先ほどの快適なもの、美しいもの、崇高なもの、(端的に)善いものは、カントの理論体系においてどのように配置されているのでしょうか?
カントは、欲求能力の高次の実現に「善いもの」、感情能力の高次の実現に「美しいものと崇高なもの」、低次の実現に「快適なもの」を位置づけます。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2025S 國分功一郎
こちらの表を見てください。このように配置された4つの枠(象限)に、右上から反時計回りに番号を振ってみます。
すると、お気づきの方もいるかと思いますが、快の対象は4つの象限に不均等に配置されていることがわかります。
そう、第3象限(欲求能力の低次の実現)には、快はないとされています。これは驚くべきことです。なぜなら、私たちの日常生活はほとんどこの領域、つまり「何かのためにやる」ということで成り立っているからです。
例えばいい会社に入るために受験勉強を頑張る、単位を取るために授業に出るのも、この第3象限に当てはまります。
しかし、カントはそこに満足はあっても快はないと言います。なぜなら、自分で自分の行動を決めるのではなく、何かに駆り立てられて行動しているからです。例えば、いい会社に入るために受験勉強をしようと考える時には、いい会社に入るのが良いことだという社会通念に駆り立てられていると言えます。カントは、このような行為を「病的(パトローギッシュ)」とさえ表現しています。
一方で、第4象限(感情能力の低次の実現)は、高次の実現である第1象限と第2象限とグルーピングされています。これを踏まえると、カントはこの第4象限、つまり「享受の快」を重視しているのではないか、とも考えられるのです。
手段と目的からみる「享受の快」
この4つの象限を目的と手段という観点で見つめ直したとき、「享受の快」の特徴が浮かびあがります。カントにおいて、目的は「あるべき姿」を意味するもので、第2象限の善は人間のあるべき姿、目的ということになります。
また、カントによれば「美」の体験というのは、あらかじめ「こうであるべきだ」とわかっているわけではないものを見て、つい「こうあるべきだ」と感じてしまうことです。
國分先生は、彼岸花を初めて見たときの経験を例に挙げています。庭の草むしり中にふと目にし、その複雑で独特な形に「なんだこれは?」と思いながらも、心惹かれ「きれいだ」と感じた経験です。
また、カントは崇高なものというのは、圧倒してくる自然物を前にしたときに、自らの人間性というあるべき姿(目的)を再発見することだと言います。
つまり、快の対象として挙げられた4つのうち、「快適なもの」以外は目的性、「こうあるべき」というべき性質があります。
カントが快適なものを説明する際に最初にあげている例は、ワインです。ただおいしく、ただ単に満足を与えるもので、そこに目的性はありません。
しかし、この中で特に問題になるのが、第4象限と第3象限の区別です。
たとえば、「今日は疲れたからビールを飲みたい」と思っているとしましょう。このとき、目的は「リラックスすること」、ビールはその手段です。実際に飲んで「やっと飲めた」と感じたときの快は、「目的を達成したこと」による満足です。
しかし、ここでの「快」と、ビールそのものの味わいが与える「快」とは異なります。「おいしい」と感じるその感覚は、「享受の快」として第4象限に属するものです。
食事についても同様です。栄養摂取が目的であることは間違いありませんが、たとえ栄養のために食べていたとしても、「今日のご飯はなんだかおいしい」と感じる瞬間には、栄養という目的を超えた「享受の快」が生まれているのです。
つまり、目的達成による満足と、対象そのものが与える快とは、概念的にも区別されなければなりません。
嗜好品と違法薬物の明確な区別、そして依存症の問題
ここで皆さんに考えていただきたいのは、「もし、第4象限が失われ、第3象限のみになると何が起こるか?」ということです。
たとえばアルコール飲料。これが第4象限の「享受の快」を失い、第3象限的な「酔うための手段」としてだけ消費されると、アルコール依存という病的状態へと至ります。このとき、飲酒は何らかの苦しみから逃れるための手段になっていることがあります。
さらに深刻な例が薬物依存です。薬は通常、何らかの症状を抑えるためというような明確な目的があり、手段となるものです。薬は人間が生きていくうえで大切なものですが、それを日常生活が送れない状態になるまで使ってしまうのが薬物依存です。薬には「享受の快」を与える要素が全くないため、純粋に第3象限に閉じ込められていると言えます。
こうした依存症の多くは、人生の苦しみと深く関わっており、その苦しみから逃れる手段としてアルコールや薬を使ってしまうことがあるということを、私たちは心にとめておかなければなりません。
まとめ
「享受の快」がはく奪された「生」、つまり第3象限のみで生きている状態では、すべてが目的と手段の連関の中に組み込まれてしまいます。何かを楽しむことが全くなくなってしまったとき、人は第3象限だけで生きることになるのです。
では、どうすればそのような状態を避けられるのでしょうか?
それは一概には言えないものの、人間にとって「快適なもの」、つまり「享受の快」をちゃんと取っておくことが大事なのではないかと國分先生は言います。
今の世の中では、このようなものを徹底的に排除する傾向にあると言えます。たとえば、たばこ、酒、砂糖のようなものは、健康の観点から忌避されつつあります。流行りである「コスパ」や「タイパ」も、すべて目的と手段だけで回していく考え方で、世の中全体が第3象限に切り詰められていっているとも言えます。
生の中で確かに大事なはずの「ただ楽しむだけのもの」。それが失われていく世の中で良いのだろうか?と國分先生は問いかけています。
講義動画では、ここでは紹介しきれなかった話題も少なくありません。また、内容だけでなく、哲学的な考察を日常と地続きの言葉を使い明快に解説する國分先生の語り口も動画の魅力です。
<文/RF(東京大学学生サポーター)>
今回紹介した講義:学術フロンティア講義(30年後の世界へ――変わる教養、変える教養) 第2回 享受の快--カントと嗜好品 國分 功一郎先生
●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。
そう問われたとき、私たちは意外と答えに詰まります。自分が何をしているときに楽しいのか、どのような条件を満たすと「楽しい」と感じるのか、実は明確には分かっていないのかもしれません。
哲学の世界では、一般に「美しい」の方が「楽しい」よりも高尚なものとされてきました。そのため、「美しい」に関する議論は数多く存在しますが、「楽しい」についての哲学的議論は多くありません。楽しみそのもの、そして楽しむためだけに存在する「嗜好品」についても同様です。
この「嗜好品」という言葉はドイツ語の「Genußmittel」を翻訳したものです。「Genießen」は「楽しむ」「味わう」といった意味の動詞で、「Genuß」はその名詞形。「Mittel」は「手段」ですから、「Genußmittel」とは「楽しむための手段」、すなわち嗜好品というわけです。
講義では、「Genuß」を「享受の快」と訳し、この概念を通してカントが人間の楽しみをどう捉えていたのか、そしてその考えが現代社会においてどのような意味を持ちうるのかを考えていきます。
今回ご紹介するのは、2025年度開講の学術フロンティア講義(30年後の世界へーー変わる教養、変える教養)「第2回 享受の快--カントと嗜好品」。講師は『暇と退屈の倫理学』『手段からの解放』などの著書で知られる哲学者・國分功一郎先生です。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2025S 國分功一郎
カントの理論体系
早速、本題に入ります。まずは、カントの理論体系を踏まえ「享受の快」がどう位置付けられているか見ていきます。
カントには三つの主著、『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』があり、それぞれ人間の異なる能力を扱っています。この三冊をもって、カントは人間の経験全体を説明しようと試みました。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2025S 國分功一郎
『純粋理性批判』では認識能力を、『実践理性批判』では欲求能力、すなわち「善をイメージしてそれを実現したいと欲求して行為する」能力を吟味しています。そして、『判断力批判』が対象とするのは人間の「感情能力」です。(ここでの「批判」はケチをつけることではなく、吟味するという意味です。)
表が示しているように、カントはそれぞれの能力を高次と低次に区別しています。たとえば、欲求能力においては「やらなければならないからやる」ことが高次とされ、「何かのためにやる」ことは低次とされます。
人間の「快」は4種類しかない?
そして、カントによれば、人間にとっての「快」は4種類に分類されます。(「快」は、快楽や快感とも訳せますが意味が限定されてしまうのでここでは「快」と訳します。)
快の対象は、快適なもの、美しいもの、崇高なもの、(端的に)善いものの4つのいずれかに当てはまると考えられ、このうち「快適なもの」(Angenehmen)という概念が、「享受の快」に結び付けられています。
4つの快の対象の配置
では、先ほどの快適なもの、美しいもの、崇高なもの、(端的に)善いものは、カントの理論体系においてどのように配置されているのでしょうか?
カントは、欲求能力の高次の実現に「善いもの」、感情能力の高次の実現に「美しいものと崇高なもの」、低次の実現に「快適なもの」を位置づけます。
UTokyo Online Education 学術フロンティア講義 2025S 國分功一郎
こちらの表を見てください。このように配置された4つの枠(象限)に、右上から反時計回りに番号を振ってみます。
すると、お気づきの方もいるかと思いますが、快の対象は4つの象限に不均等に配置されていることがわかります。
そう、第3象限(欲求能力の低次の実現)には、快はないとされています。これは驚くべきことです。なぜなら、私たちの日常生活はほとんどこの領域、つまり「何かのためにやる」ということで成り立っているからです。
例えばいい会社に入るために受験勉強を頑張る、単位を取るために授業に出るのも、この第3象限に当てはまります。
しかし、カントはそこに満足はあっても快はないと言います。なぜなら、自分で自分の行動を決めるのではなく、何かに駆り立てられて行動しているからです。例えば、いい会社に入るために受験勉強をしようと考える時には、いい会社に入るのが良いことだという社会通念に駆り立てられていると言えます。カントは、このような行為を「病的(パトローギッシュ)」とさえ表現しています。
一方で、第4象限(感情能力の低次の実現)は、高次の実現である第1象限と第2象限とグルーピングされています。これを踏まえると、カントはこの第4象限、つまり「享受の快」を重視しているのではないか、とも考えられるのです。
手段と目的からみる「享受の快」
この4つの象限を目的と手段という観点で見つめ直したとき、「享受の快」の特徴が浮かびあがります。カントにおいて、目的は「あるべき姿」を意味するもので、第2象限の善は人間のあるべき姿、目的ということになります。
また、カントによれば「美」の体験というのは、あらかじめ「こうであるべきだ」とわかっているわけではないものを見て、つい「こうあるべきだ」と感じてしまうことです。
國分先生は、彼岸花を初めて見たときの経験を例に挙げています。庭の草むしり中にふと目にし、その複雑で独特な形に「なんだこれは?」と思いながらも、心惹かれ「きれいだ」と感じた経験です。
また、カントは崇高なものというのは、圧倒してくる自然物を前にしたときに、自らの人間性というあるべき姿(目的)を再発見することだと言います。
つまり、快の対象として挙げられた4つのうち、「快適なもの」以外は目的性、「こうあるべき」というべき性質があります。
カントが快適なものを説明する際に最初にあげている例は、ワインです。ただおいしく、ただ単に満足を与えるもので、そこに目的性はありません。
しかし、この中で特に問題になるのが、第4象限と第3象限の区別です。
たとえば、「今日は疲れたからビールを飲みたい」と思っているとしましょう。このとき、目的は「リラックスすること」、ビールはその手段です。実際に飲んで「やっと飲めた」と感じたときの快は、「目的を達成したこと」による満足です。
しかし、ここでの「快」と、ビールそのものの味わいが与える「快」とは異なります。「おいしい」と感じるその感覚は、「享受の快」として第4象限に属するものです。
食事についても同様です。栄養摂取が目的であることは間違いありませんが、たとえ栄養のために食べていたとしても、「今日のご飯はなんだかおいしい」と感じる瞬間には、栄養という目的を超えた「享受の快」が生まれているのです。
つまり、目的達成による満足と、対象そのものが与える快とは、概念的にも区別されなければなりません。
嗜好品と違法薬物の明確な区別、そして依存症の問題
ここで皆さんに考えていただきたいのは、「もし、第4象限が失われ、第3象限のみになると何が起こるか?」ということです。
たとえばアルコール飲料。これが第4象限の「享受の快」を失い、第3象限的な「酔うための手段」としてだけ消費されると、アルコール依存という病的状態へと至ります。このとき、飲酒は何らかの苦しみから逃れるための手段になっていることがあります。
さらに深刻な例が薬物依存です。薬は通常、何らかの症状を抑えるためというような明確な目的があり、手段となるものです。薬は人間が生きていくうえで大切なものですが、それを日常生活が送れない状態になるまで使ってしまうのが薬物依存です。薬には「享受の快」を与える要素が全くないため、純粋に第3象限に閉じ込められていると言えます。
こうした依存症の多くは、人生の苦しみと深く関わっており、その苦しみから逃れる手段としてアルコールや薬を使ってしまうことがあるということを、私たちは心にとめておかなければなりません。
まとめ
「享受の快」がはく奪された「生」、つまり第3象限のみで生きている状態では、すべてが目的と手段の連関の中に組み込まれてしまいます。何かを楽しむことが全くなくなってしまったとき、人は第3象限だけで生きることになるのです。
では、どうすればそのような状態を避けられるのでしょうか?
それは一概には言えないものの、人間にとって「快適なもの」、つまり「享受の快」をちゃんと取っておくことが大事なのではないかと國分先生は言います。
今の世の中では、このようなものを徹底的に排除する傾向にあると言えます。たとえば、たばこ、酒、砂糖のようなものは、健康の観点から忌避されつつあります。流行りである「コスパ」や「タイパ」も、すべて目的と手段だけで回していく考え方で、世の中全体が第3象限に切り詰められていっているとも言えます。
生の中で確かに大事なはずの「ただ楽しむだけのもの」。それが失われていく世の中で良いのだろうか?と國分先生は問いかけています。
講義動画では、ここでは紹介しきれなかった話題も少なくありません。また、内容だけでなく、哲学的な考察を日常と地続きの言葉を使い明快に解説する國分先生の語り口も動画の魅力です。
<文/RF(東京大学学生サポーター)>
今回紹介した講義:学術フロンティア講義(30年後の世界へ――変わる教養、変える教養) 第2回 享受の快--カントと嗜好品 國分 功一郎先生
●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。