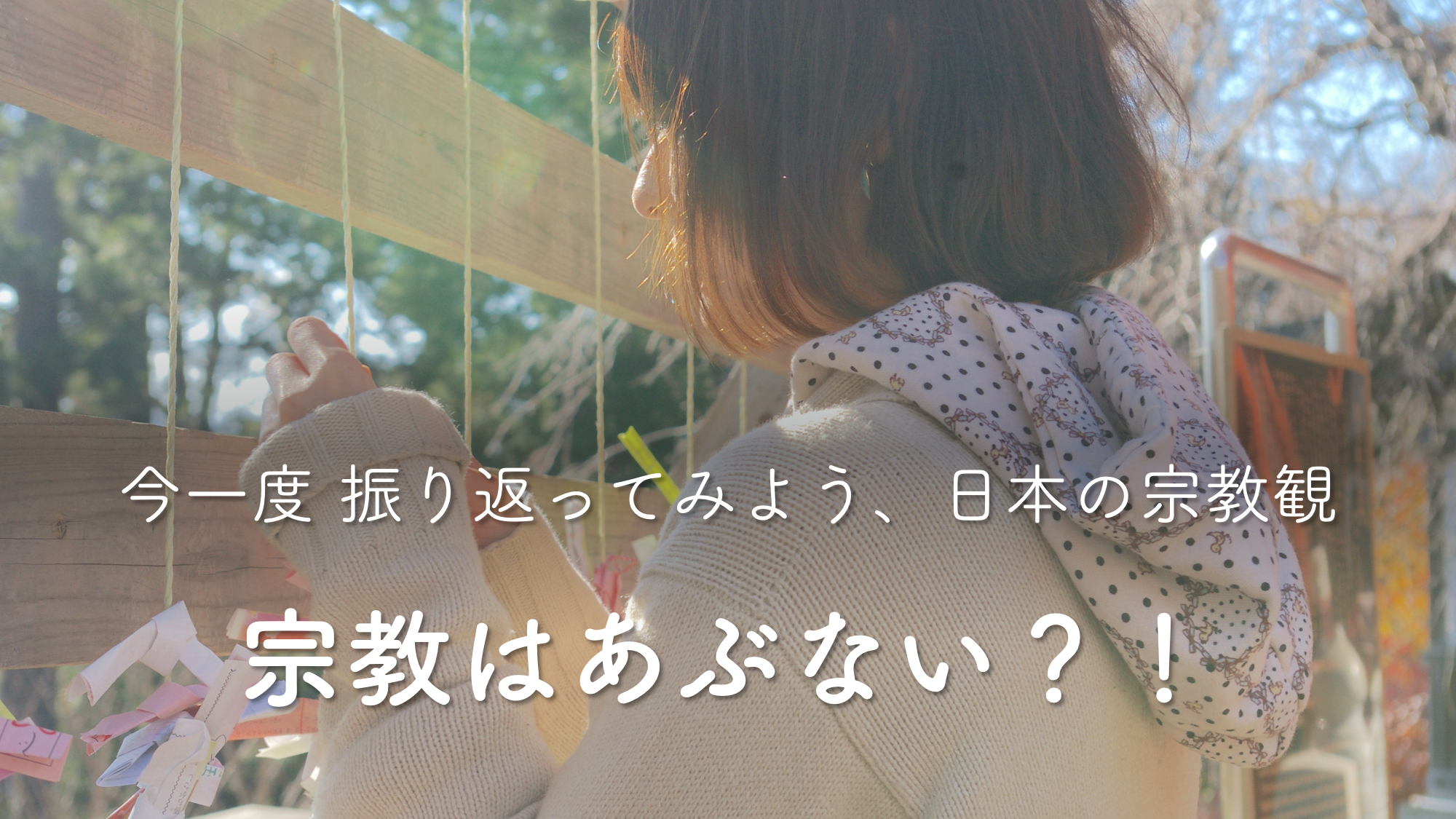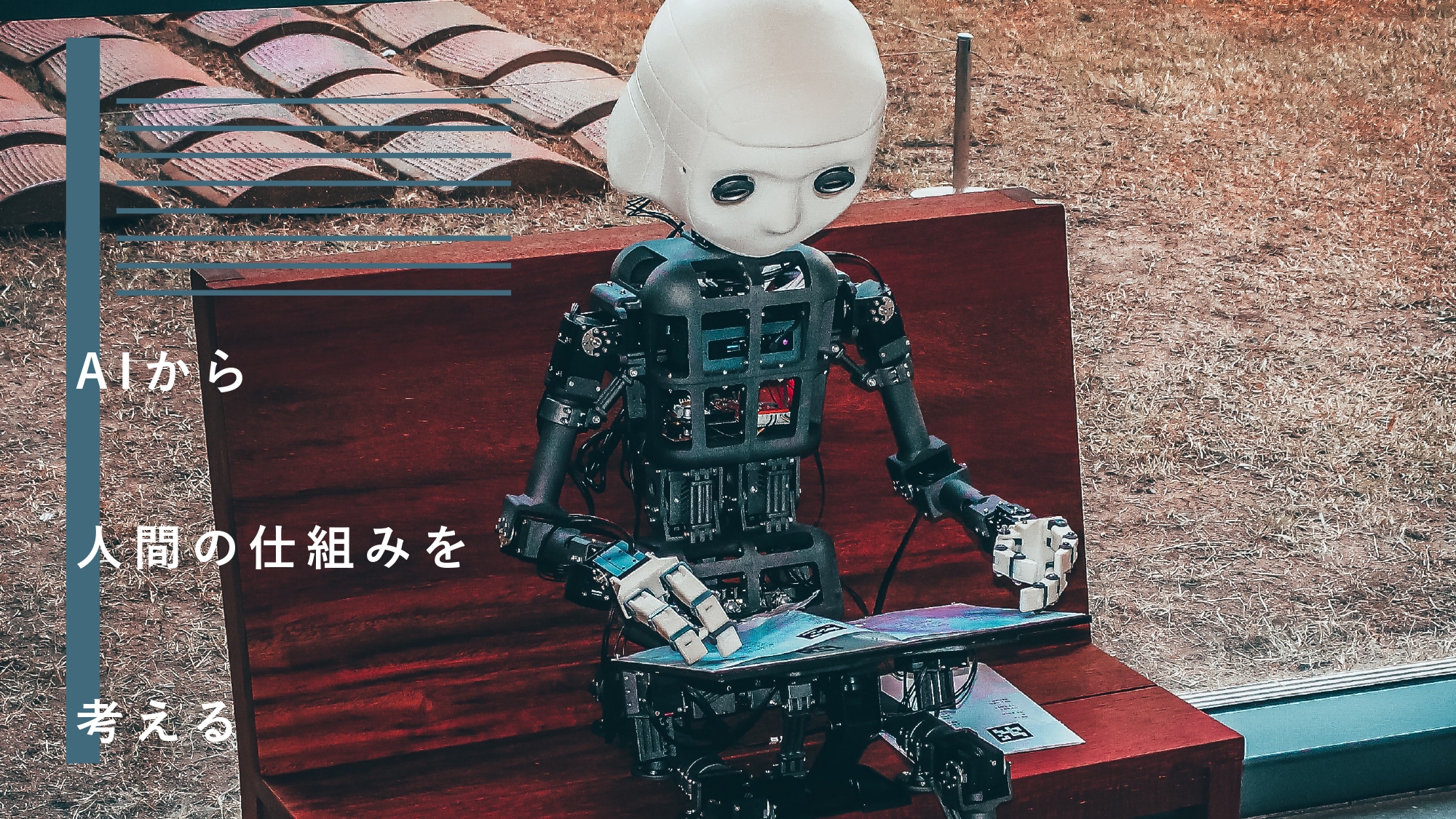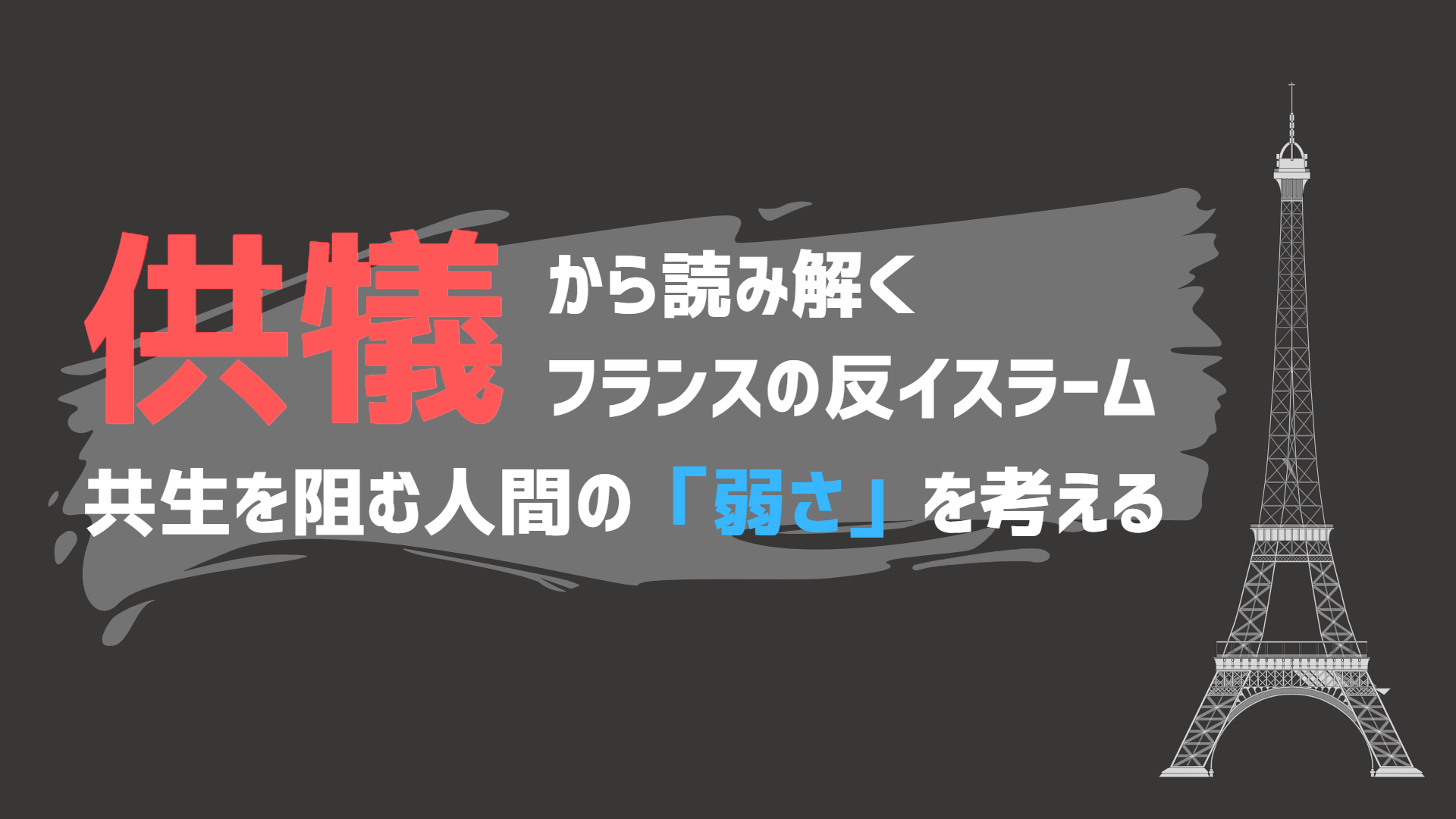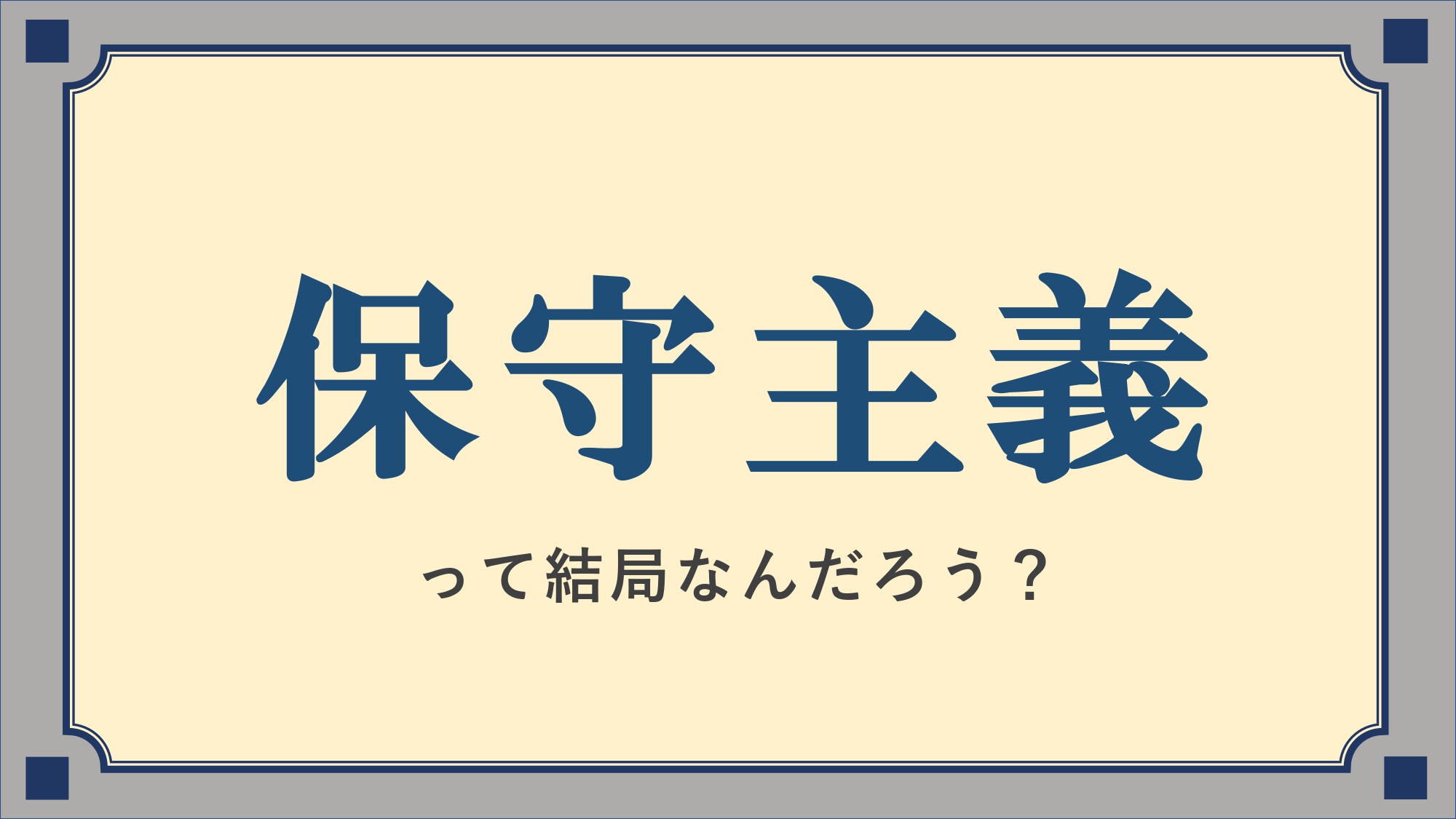2022/09/14
あなたにとって、「家族」とはどのような存在ですか?
あなたにとって、「家族」とは誰を指しますか?
本来であれば、血縁や婚姻関係で客観的に、かつ明確に記述できるはずの「家族」。
しかし、いざ自分の身に置き換えて「家族」を考えた時、
客観的に定義されるはずの自分の「家族」と、自分が認知する「家族」との間にギャップを感じたことはありませんか?
なんだか不思議な話ですよね……。
そんな、家族の「境界」について、社会学者の赤川先生と一緒に考えてみませんか?
「家族」の定義や境界線をめぐる、とても面白い講義をご紹介します。
1.家族定義の不可能性~社会学の観点より~
あなたにとって誰が「家族」なのか、
「家族」というのはどのような「意味」を持っているのか
これらは社会学において普遍的なテーマであると考えられています。
まず始めに、いくつかの観点から、社会学における家族の定義について考えていきます。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
① 血縁と婚姻の組み合わせによる客観的な記述は可能か
ある個人が親族内に占める位置づけは、血縁と婚姻の組み合わせで客観的に記述できるように見えます。
ところが世の中には色々な社会があり、生物学的には父親に見えるような人を父親とみなさずに、父親はいないものとして扱う社会も実際にあります。
このことから、家族とは、血縁・婚姻関係で客観的に定義することが難しいとも考えられます。
② 家族が果たす機能による定義の可能性
血縁・婚姻関係による客観的な定義は難しいということが分かりました。
では、家族が果たす機能、つまり子どもの基礎的社会や成人のパーソナリティ安定化といった機能での定義はどうでしょうか?
すると、じゃあそういう機能を果たさない家族は家族ではないのか、という話になると講師は言います。
例えば、愛し合っていなかったり性行為をしなかったりする夫婦は家族ではないのかという疑問に突き当たるわけです。
家族とされる成員の範囲は、研究者が客観的に確定できるかと言われると、
「できない」という傾向になってきていると講師は述べます。
学者は家族を客観的に定義しようと頑張るが、結局「無理だ」という結論になるのだそうです。
2.家族の認知的境界~ファミリー・アイデンティティ(F.I.)論~
ここで一つ、家族の認知的境界に焦点をあてた理論である、ファミリー・アイデンティティ論を紹介します。
ファミリー・アイデンティティ論とは、社会学者の上野千鶴子氏が提唱したものです。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
上野氏は、家族は血縁やDNAといった実体よりも、より多くの意識の中に存在するとしました。
なぜなら、
「自分はこの人を家族だと思うと定義しても、この人が自分のことを家族と思ってくれなければ、家族としてのコミュニケーションは難しい」からだそうです。
そのため上野氏は、
家族というのは、そのような意味できわめて「相互主観的」な現象であるとしました。
実際に、意識と形態の面で非伝統的な50の類型の人たちに対して行った、家族の「境界の定義」を尋ねる調査において、最初に分かった一番重要なことは、
親子・配偶者間でも、家族の範囲はずれる場合がある
ということだったそうです。
3.家族境界の歴史的変容~血縁/同居から親密性へ~
今まで述べてきたように、家族の境界に関しては絶対の回答はなく、それぞれに腐心しながら、家族の境界を設定しています。
しかしながら、その境界設定は歴史的に変化してきています。
近年明らかに浮上しているのは、親密性の基準であると講師は言います。
つまり、親しさや愛情のようなものが家族の境界を決める基準になるという考え方です。
これはある意味、選択の対象として家族が表れているとも言えます。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
4.家族とは、相手を思いやる気持ちや愛情の深さ?
このように、家族を、愛情や親しさをもって定義しようとする傾向を、アンソニー・ギデンズは、「純粋な関係性」と呼びました。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
近代社会とは、色々な制度を自己反省して問い直していく社会であり、
あらゆる制度や慣習が、自由や平等といった民主的な価値観によって見直されていく。
その中で、家族や性の領域もその例外ではなく、
父親、母親、子どもといった役割もまた、
利害や慣習に基づかず、自発的に選び取る対象となる。
このようにギデンズは述べています。
このような、「純粋な関係性」は、一見リベラルで民主的で、とても良い理想的な状態に見えます。
しかし、こういう関係性には困難もあることをギデンズは指摘しています。
純粋な関係性では、社会の中でどういうふうに自分たちがふるまうべきかを、
その都度その都度二人で選択しながら、合意して決めていく必要があります。
そうすると、「家族の調整コスト」問題が浮上します。
つまり、1から10まで全部自分たちで決めなければならず、自分たちで自発的に選び取って、合意的に選択していくというのもそれはそれなりに困難があるということです。
これは、人間に課された大きな問いであると講師は述べます。
5.まとめ
家族の認知、家族の規範、家族の意味というのは、時代によって変わったり、組織によって変わったり、人によって違ったりします。
ですが、人は必死でそこに意味を与えて、家族というものを作り上げています。
どういう良い家族を作っていくかが、社会学者に与えられた課題であると講師は言います。
様々な視点から、「家族」の定義や境界線について考えていくこの講義を通して、
普段は恐らく考えることの少ないであろう、「家族」という身近なテーマについて、ふと立ち止まって考えてみませんか?
★おまけとして‥‥
実はこの講義、もう一つ大きなテーマがあります。
それはずばり、ペットです。
ペットを家族とみなす人の割合は昔に比べて増加しているそうです。
山田昌弘氏は、
家族というのは、「自分を自分としてみてくれ、自分であることを識別してくれる存在」であり、
この、かけがえのなさ、自分らしさの感覚を人間の家族に求めることは難しいため、「理想の家族」としての投影先がペットになる。
むしろ、ペットのほうが家族らしく、家族の方が家族らしくないかもしれない
と述べているそうです。
ペットは家族か、人はなぜペットを飼うのか、そして、ペットの死はなぜあんなにも辛いのか
それらの問いについて考えることは、
私たちが「家族」に求めるもの、私たちにとっての「家族」の意味を考えることにもまた、つながっていくのではないでしょうか。
今回紹介した講義:境界線をめぐる旅(朝日講座「知の冒険—もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2013年度講義)第4回 家族とは誰のことか-家族の境界をめぐって 赤川 学先生
<文/東京大学オンライン教育支援サポーター>
あなたにとって、「家族」とは誰を指しますか?
本来であれば、血縁や婚姻関係で客観的に、かつ明確に記述できるはずの「家族」。
しかし、いざ自分の身に置き換えて「家族」を考えた時、
客観的に定義されるはずの自分の「家族」と、自分が認知する「家族」との間にギャップを感じたことはありませんか?
なんだか不思議な話ですよね……。
そんな、家族の「境界」について、社会学者の赤川先生と一緒に考えてみませんか?
「家族」の定義や境界線をめぐる、とても面白い講義をご紹介します。
1.家族定義の不可能性~社会学の観点より~
あなたにとって誰が「家族」なのか、
「家族」というのはどのような「意味」を持っているのか
これらは社会学において普遍的なテーマであると考えられています。
まず始めに、いくつかの観点から、社会学における家族の定義について考えていきます。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
① 血縁と婚姻の組み合わせによる客観的な記述は可能か
ある個人が親族内に占める位置づけは、血縁と婚姻の組み合わせで客観的に記述できるように見えます。
ところが世の中には色々な社会があり、生物学的には父親に見えるような人を父親とみなさずに、父親はいないものとして扱う社会も実際にあります。
このことから、家族とは、血縁・婚姻関係で客観的に定義することが難しいとも考えられます。
② 家族が果たす機能による定義の可能性
血縁・婚姻関係による客観的な定義は難しいということが分かりました。
では、家族が果たす機能、つまり子どもの基礎的社会や成人のパーソナリティ安定化といった機能での定義はどうでしょうか?
すると、じゃあそういう機能を果たさない家族は家族ではないのか、という話になると講師は言います。
例えば、愛し合っていなかったり性行為をしなかったりする夫婦は家族ではないのかという疑問に突き当たるわけです。
家族とされる成員の範囲は、研究者が客観的に確定できるかと言われると、
「できない」という傾向になってきていると講師は述べます。
学者は家族を客観的に定義しようと頑張るが、結局「無理だ」という結論になるのだそうです。
2.家族の認知的境界~ファミリー・アイデンティティ(F.I.)論~
ここで一つ、家族の認知的境界に焦点をあてた理論である、ファミリー・アイデンティティ論を紹介します。
ファミリー・アイデンティティ論とは、社会学者の上野千鶴子氏が提唱したものです。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
上野氏は、家族は血縁やDNAといった実体よりも、より多くの意識の中に存在するとしました。
なぜなら、
「自分はこの人を家族だと思うと定義しても、この人が自分のことを家族と思ってくれなければ、家族としてのコミュニケーションは難しい」からだそうです。
そのため上野氏は、
家族というのは、そのような意味できわめて「相互主観的」な現象であるとしました。
実際に、意識と形態の面で非伝統的な50の類型の人たちに対して行った、家族の「境界の定義」を尋ねる調査において、最初に分かった一番重要なことは、
親子・配偶者間でも、家族の範囲はずれる場合がある
ということだったそうです。
3.家族境界の歴史的変容~血縁/同居から親密性へ~
今まで述べてきたように、家族の境界に関しては絶対の回答はなく、それぞれに腐心しながら、家族の境界を設定しています。
しかしながら、その境界設定は歴史的に変化してきています。
近年明らかに浮上しているのは、親密性の基準であると講師は言います。
つまり、親しさや愛情のようなものが家族の境界を決める基準になるという考え方です。
これはある意味、選択の対象として家族が表れているとも言えます。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
4.家族とは、相手を思いやる気持ちや愛情の深さ?
このように、家族を、愛情や親しさをもって定義しようとする傾向を、アンソニー・ギデンズは、「純粋な関係性」と呼びました。
UTokyo Onine Education 東京大学朝日講座 「知の冒険」Copyright 2013, 赤川学
近代社会とは、色々な制度を自己反省して問い直していく社会であり、
あらゆる制度や慣習が、自由や平等といった民主的な価値観によって見直されていく。
その中で、家族や性の領域もその例外ではなく、
父親、母親、子どもといった役割もまた、
利害や慣習に基づかず、自発的に選び取る対象となる。
このようにギデンズは述べています。
このような、「純粋な関係性」は、一見リベラルで民主的で、とても良い理想的な状態に見えます。
しかし、こういう関係性には困難もあることをギデンズは指摘しています。
純粋な関係性では、社会の中でどういうふうに自分たちがふるまうべきかを、
その都度その都度二人で選択しながら、合意して決めていく必要があります。
そうすると、「家族の調整コスト」問題が浮上します。
つまり、1から10まで全部自分たちで決めなければならず、自分たちで自発的に選び取って、合意的に選択していくというのもそれはそれなりに困難があるということです。
これは、人間に課された大きな問いであると講師は述べます。
5.まとめ
家族の認知、家族の規範、家族の意味というのは、時代によって変わったり、組織によって変わったり、人によって違ったりします。
ですが、人は必死でそこに意味を与えて、家族というものを作り上げています。
どういう良い家族を作っていくかが、社会学者に与えられた課題であると講師は言います。
様々な視点から、「家族」の定義や境界線について考えていくこの講義を通して、
普段は恐らく考えることの少ないであろう、「家族」という身近なテーマについて、ふと立ち止まって考えてみませんか?
★おまけとして‥‥
実はこの講義、もう一つ大きなテーマがあります。
それはずばり、ペットです。
ペットを家族とみなす人の割合は昔に比べて増加しているそうです。
山田昌弘氏は、
家族というのは、「自分を自分としてみてくれ、自分であることを識別してくれる存在」であり、
この、かけがえのなさ、自分らしさの感覚を人間の家族に求めることは難しいため、「理想の家族」としての投影先がペットになる。
むしろ、ペットのほうが家族らしく、家族の方が家族らしくないかもしれない
と述べているそうです。
ペットは家族か、人はなぜペットを飼うのか、そして、ペットの死はなぜあんなにも辛いのか
それらの問いについて考えることは、
私たちが「家族」に求めるもの、私たちにとっての「家族」の意味を考えることにもまた、つながっていくのではないでしょうか。
今回紹介した講義:境界線をめぐる旅(朝日講座「知の冒険—もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2013年度講義)第4回 家族とは誰のことか-家族の境界をめぐって 赤川 学先生
<文/東京大学オンライン教育支援サポーター>