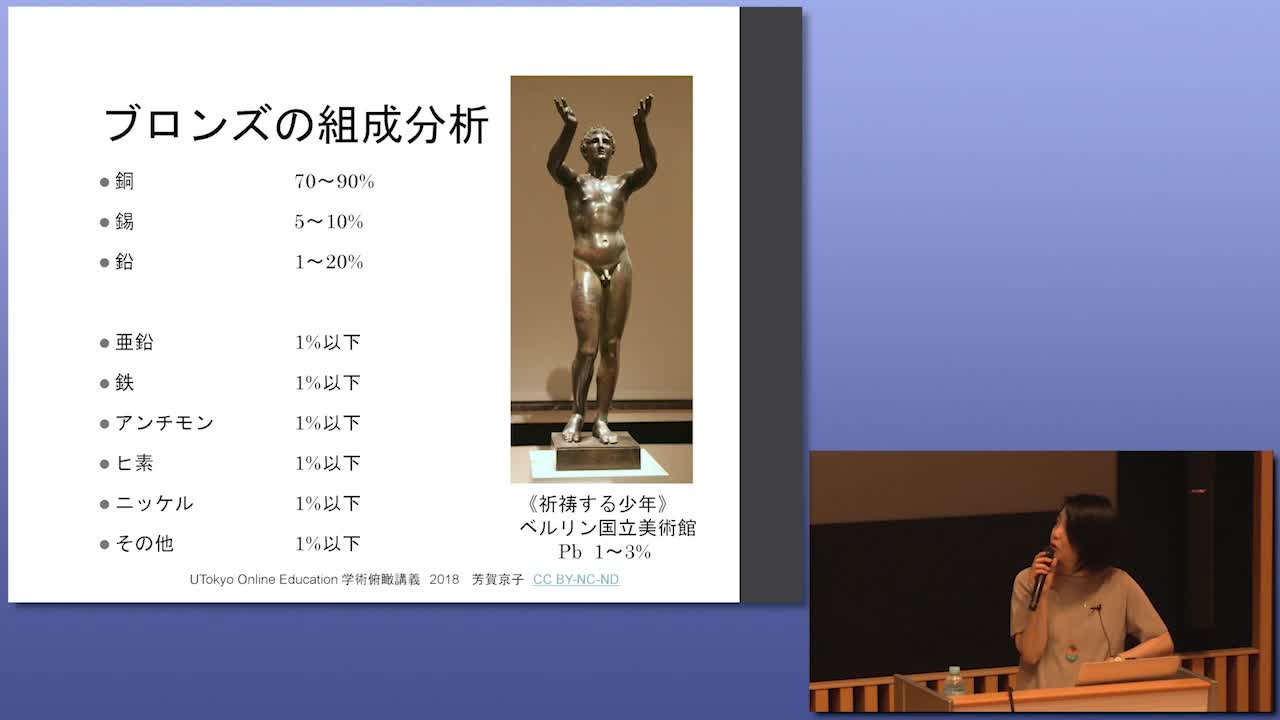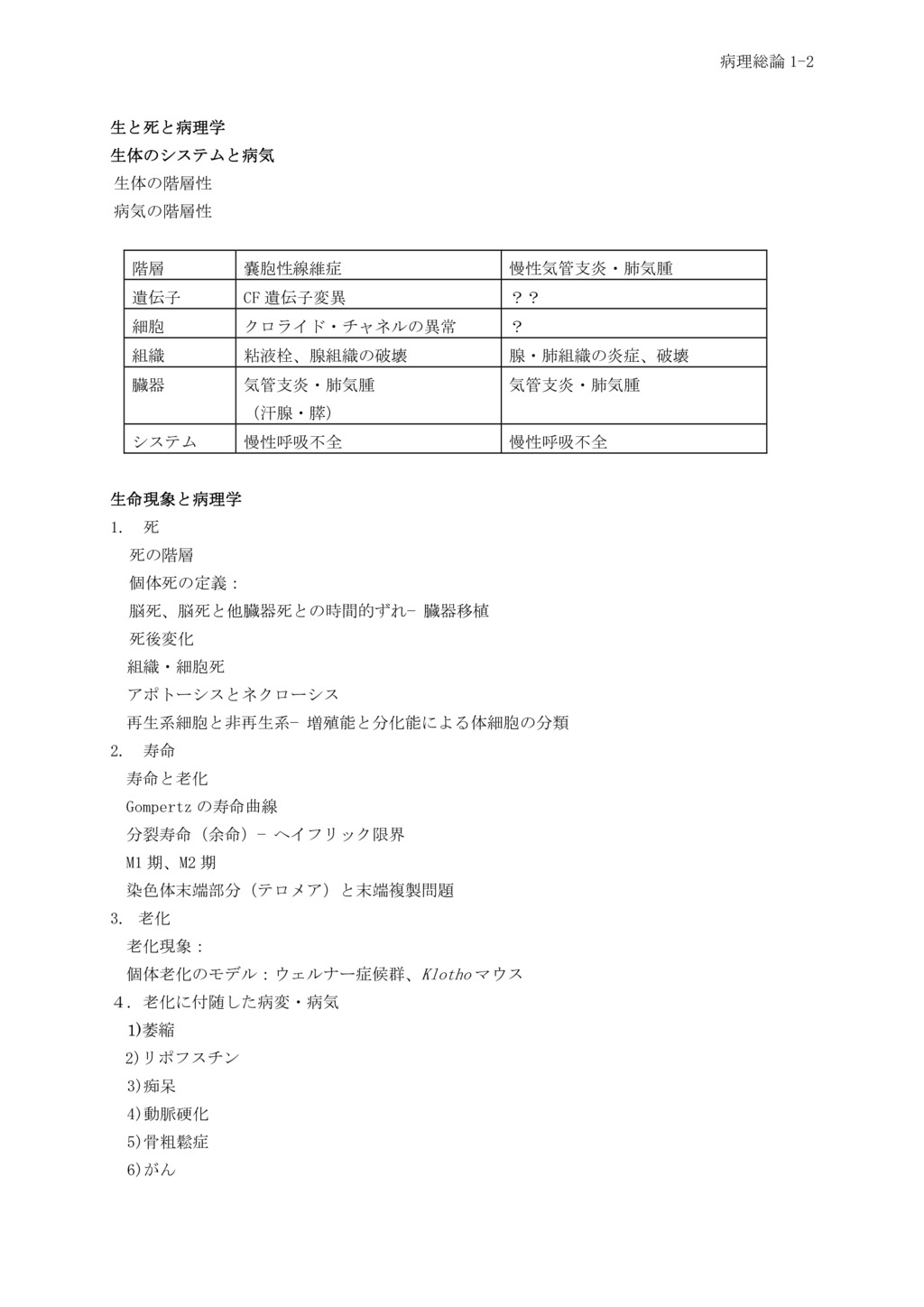2021年度開講
30年後の世界へ ― 学問とその“悪”について(学術フロンティア講義)
2019年に発足した東アジア藝文書院(East Asian Academy for New Liberal Arts, EAA)は、「東アジアからのリベラルアーツ」を標榜しつつ、北京大学をはじめとする国際的な研究ネットワークの下に、「世界」と「人間」を両面から問い直す新しい学問の創出を目指す、東京大学の研究教育センターです。学問はわたしたちにただ単に未来を予測させるものではありません。そうではなく、わたしたちは学問をすることによって、わたしたちが意志して望む未来を創出しているのです。そこでわたしたちは、学問のフロンティアであるここ駒場に集う先生方とともに、皆さんが社会の中心で活躍しているであろう「30年後の世界」に向かって、学問的な問いを開く試みを発足当初から行っています。
2020年以来、人類は新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の災禍に苦しんでいます。しかし、この災禍は、実は、「すでに気づかれていた弊害」が一気に噴出したものに過ぎないのではないかと、EAAの中島隆博院長は問うています(EAAオンラインワークショップ「感染症の哲学」2020年4月22日)。地球の南北どちらに住んでいるかによって生存条件が大きく異なり、また、1%の人口が他の99%の人々の富の総量を所有しているとすら言われる構造的な格差問題、テクノロジーの高度化による生命倫理の動揺や社会生活の一望監視化、少子高齢化の急速な進行、グローバルな人と経済の流動がもたらすさまざまな摩擦や社会分断などなど。COVID-19の世界的流行が示しているのは、感染によって生じる疾病がみごとなまでに、このような「すでに気づかれていた」構造的な弊害を、その構図通りになぞっていることです。コロナウィルスの人類への感染という現象自体が、自然収奪型の近代産業経済が行き着くべくして行き着いた結果であるという声もあります。
「すでに気づかれていた弊害」のひとつひとつをすべて一気に解決する術はどこにもないでしょうし、それを目指したところでよい結果は望めないでしょう。それでもわたしたちは、学問の名において、想像力を解放し、よりよい未来を望むことができるはずです。なぜなら、学問とは「到来すべきもの」を公に向かって告げるものにほかならないからです。未来に進むべき方向を指し示すのが学問によって灯される希望の光であることは、古代ギリシャの昔から変わらぬ真理であるはずです。
しかし、学問を行うわたしたちが、学問こそが善であると頑なに信じているだけでは独善に過ぎません。学問は、そのある部分では、無垢であるどころか、巨大な「悪」に加担してしまっているのではないでしょうか。もしかすると学問は、「すでに気づかれていた弊害」の構造化に寄与し続けてきたかも知れないのです。思えば、20世紀以来、アウシュビッツや核兵器など、人類は極端な悪を自ら生み出してきました。9.11事件で幕を開けた21世紀にはグローバル資本主義と近代産業システムの功罪が深刻に問われる事態をわたしたちは経験し、「善」と「悪」の二元論では片づかない現実に直面しています。学問はこうした諸事態に対して、どのように諸事態を表象し、分析し、批判してきたでしょうか。このことを考えるとき、わたしたちはまた、学問がその「悪」に加担してきたという現実から目を逸らすことはできません。なぜかと言えば、学問の限界と難題(アポリア)を知ることこそが、新しい学問の出発点につながるはずだからです。 新しい学問の出発点は、新しい社会的想像力の出発点でもあります。わたしたちは、ゼロからでも理想からでもなく、自分たちが背負ってきた知の限界や難題を遺産として受け継ぐことで、「30年後の世界」を自分の手で作り出していくしかありません。
フランスの哲学者ジャック・ランシエールは「人間は知性を従えた意志である」と述べます。意志の出発点は、見ること、聞くこと、手探りすることであり、それらはそのまま、意志するひとりひとりの魂と能力を構成していくと彼は言います。中国の詩人顧城の詩に「闇夜はぼくに黒い瞳を与えた。だがぼくはその黒い瞳で光明を探す。」という一節があります。わたしたちの希望は、「悪」を見定め、「悪」のなかから世界を眼差そうとする意志によってこそ生まれるにちがいありません。
この授業に話題を提供するのは、駒場のいまを支え、東京大学の将来を担う先生方や、東アジアをベースに国際的に活躍する先生方ばかりです。哲学、文学、歴史学、社会学、生物学など、さまざまな分野の教員が集まり、皆さんとともに学問の望みを語る場——それがオムニバス講義「30年後の世界へ」の世界です。
わたしたちは、大学で学ぶことの醍醐味を味わいたいと渇望する多数の学生さんが参加してくれることを待ち望んでいます。
講義一覧